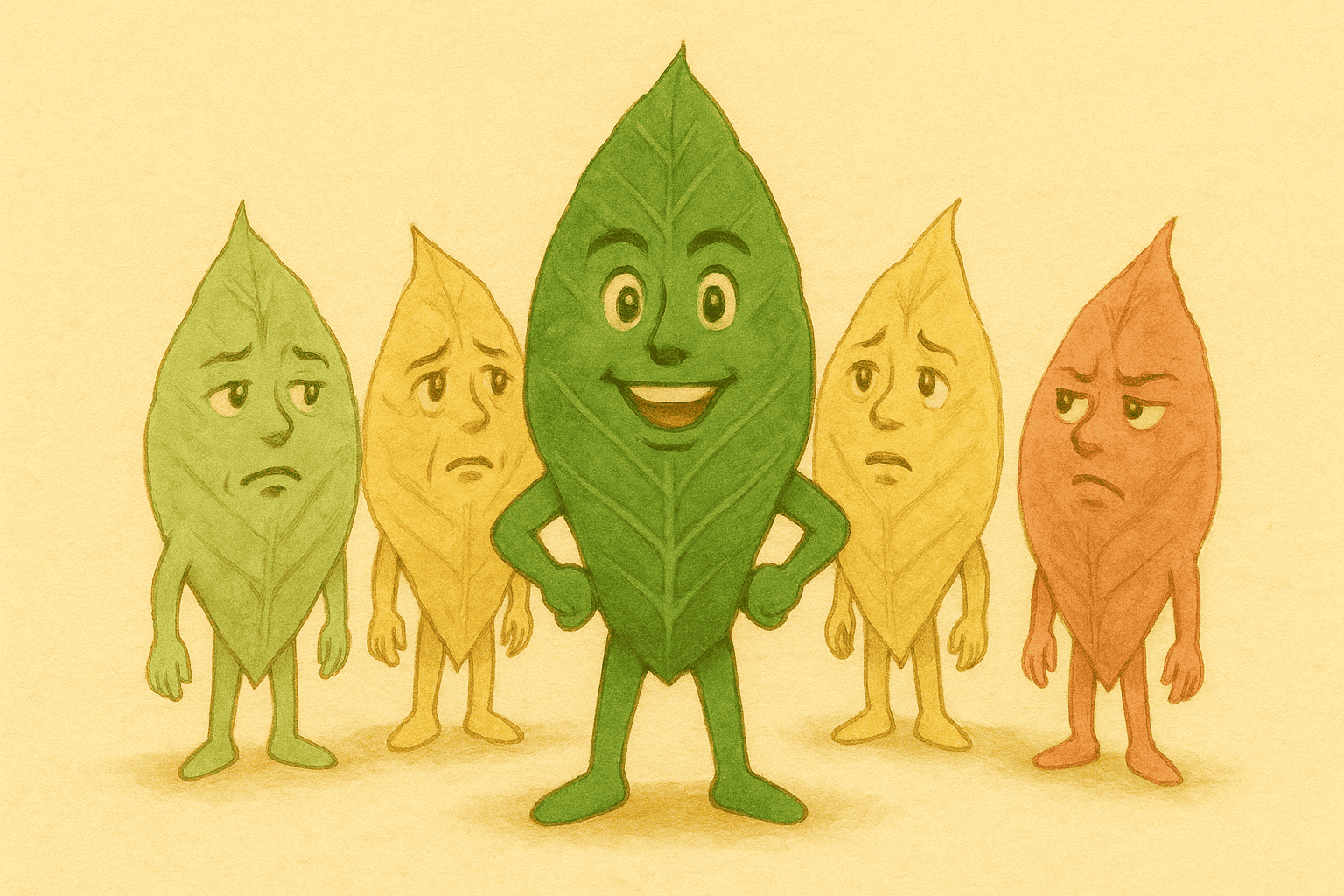🌱 光が植物の色づきに与える影響――塊根・多肉を「綺麗に大きく」育てるために
同じ株でも季節や置き場所が変わると、葉の色や質感ががらりと変わります。濃い緑で締まる時期もあれば、薄く伸びたり、赤みや黄みを帯びたり、日焼けのように褐色になることもあります。こうした見た目の違いは、光の量と質、そして温度や土壌(pH・養分・水分)などの条件によって、葉の中の色素や表面構造が変化するために生じます。本稿では、鉢植えで育てる塊根植物・多肉植物を対象に、葉色と光の関係を園芸書の言葉で丁寧にたどります。必要な用語は太字+簡潔な定義で説明し、重要な数値には信頼できる研究の出典(著者, 年)を添えます。
🧭 まずは「測る」――葉色と結びつく基本指標
色の変化を原因と結びつけるには、環境を数値で捉えることが近道です。ここでは現場で使いやすいものだけに絞って定義します。
🔦 PPFD:一定面積にどれだけ多くの「光の粒」が降り注いでいるかを表す明るさの指標。単位はµmol m⁻² s⁻¹。数値が高いほど明るい環境です。
🕒 DLI:一日の光の合計量。単位はmol m⁻² d⁻¹。明るさだけでなく点灯時間や日照時間も含めて評価できます。
🌈 赤と遠赤のバランス(R:FR):赤色(おおよそ660nm)と遠赤色(730nm)光の割合。これが低い(遠赤が多い)と、植物は「周りに遮られている」と感じて伸びやすくなります(Franklin, 2008; Pierik et al., 2009)。
🔵 青の割合:青色光の比率。青が少なすぎると徒長しやすく、適度に含むと株が締まりやすくなります(Hogewoning et al., 2010; Wollaeger & Runkle, 2015)。
🧪 SPAD:葉の「緑の濃さ(葉緑素の目安)」を手軽に測る計測値。値が高いほど濃い緑です。数値の絶対値より、同じ株での増減を見ると診断が安定します。
🌥️ 色が薄くなる・徒長する――足りない光と偏った光
葉が薄く、節と節の間が伸びて間延びする場合は、たいてい光量不足と光質の偏りが重なっています。目安として、PPFDが長時間100 µmol m⁻² s⁻¹未満で推移し、さらにR:FRが低い(遠赤過多)と、植物は光を取りに行く「伸びるモード」に入ります(Franklin, 2008)。このときSPADは下がり、色は淡く見えます。対策は、明るさと青の割合を同時に引き上げることです。青を10〜30%程度含むフルスペクトルLEDや、柔らかな直射光への段階的な移行が有効です(Hogewoning et al., 2010; Wollaeger & Runkle, 2015)。
ただし、ただ明るくすれば良いわけではありません。次章のように、急に強くすると「色が抜ける」ことがあります。光の上げ幅と慣らし方(順化)を意識してください。
⚠️ 強光で色が抜ける――急な環境変化と「葉の安全装置」の限界
日陰や室内から急に強い直射や強力なLEDに移すと、葉が黄白色〜半透明に抜けることがあります。これは、受け取った光エネルギーが多すぎて「処理しきれない」ときに起きるトラブルです。植物には余った光を熱として逃がす安全装置がありますが、処理が追いつかないと葉の中の大切な成分が壊れ、退色や日焼けへと進みます(Osmond, 1994; Murata et al., 2007; Foyer et al., 1994)。
🔁 対策は、①順化(少しずつ明るさを上げる)、②葉温を上げすぎない、③UVや直射は短時間から試すの3点です。屋外直射や夏の温室ではPPFDそのものが非常に高く、無風だと葉温が気温より+15〜20℃上がることがあります(Nobel, 1988; Leigh et al., 2006)。非接触温度計で葉温を時々チェックし、過熱を避けてください。
🍁 赤くなる――「守り」のサインと上手な付き合い方
多肉の赤や紫は見栄えがよいだけでなく、植物にとっては身を守る仕組みです。強い光やUV、夜の冷え込みなどの刺激で、葉の液胞にアントシアニン(赤紫の色素)が増えて内部を守ります(Koes et al., 2005; Brown & Jenkins, 2008)。この反応は、光を感知する仕組みをきっかけに、色素を作る酵素の働きが高まって進みます(Brown & Jenkins, 2008; Kovinich et al., 2015)。
🧩 なお、サボテンなどナデシコ目の多くはベタレイン(赤〜黄の色素)を持ち、アントシアニンと基本的に入れ替わりの関係にあります(Stafford, 1994; Clement & Mabry, 1996)。見た目は似ていますが、作られ方が違うため、反応の出方や強さには属ごとの差があります(Jain & Gould, 2015)。
🚦 赤化は「守り」の範囲なら問題ではありません。見た目を緑に戻したい場合は、直射時間を少し短くする、夜間の冷え込みを防ぐ、など環境を穏やかにしてください。なお、古い葉が暗赤〜紫になり、生育も鈍る場合はリン不足の可能性があり(Terry & Ulrich, 1974; Chalker-Scott, 1999)、施肥履歴を見直します。
🟡 黄色くなる(クロロシス)――「光」だけでは説明できないとき
黄化は養分・pH・水分の影響が大きい現象です。まず、どの葉から黄色くなるかを見ます。新芽から鮮やかに黄化し、葉脈は緑のままなら鉄(Fe)不足が典型です。下葉(古い葉)から淡く黄化するなら窒素(N)不足、葉脈間が抜けるならマグネシウム(Mg)不足を疑います(Marschner, 2012; RHS, 2019)。
💧 日本の鉢植えでは、用土のpHが7以上になるとFeやMnが吸収されにくくなり、新葉黄化が出やすくなります(Marschner, 2012)。また、過湿で根が酸素不足だと吸収そのものが落ち、同様の黄化につながります。SPADが平常より大きく下がり、新芽側に黄化が強く、pHも高めなら、まずはキレート鉄の潅水と排水・通気の改善を試してください。弱光から強光へ移した直後の一時的な黄化は、数週間で緑に戻ることが多い点も覚えておくと安心です。
🔥 焦げ・褐変――葉温の上がりすぎに要注意
真夏の直射や無風の温室で、葉の先端や縁が褐色〜黒に焦げるのは、強い光と高い葉温が重なったサインです。厚い葉は蒸散による冷却が効きにくく、条件次第で葉温が気温より+15〜20℃上がります(Nobel, 1988; Leigh et al., 2006)。また、葉に残った水滴がレンズのように働き、局所的なスポット焼けを起こすこともあります。
🛡️ 予防は、風を通して葉温を下げる、30〜50%遮光で直射のピークを和らげる、水やり直後は葉に水滴を残さない、の三本柱です(Foyer et al., 1994)。非接触温度計で時々チェックし、葉温45℃超が続かないよう管理すると失敗が減ります。
✨ 表面構造が作る色――白粉・銀葉・斑・毛
多肉の白粉(ブルーム:表面の白い粉状のワックス)や銀葉は、強い光から身を守る鎧でもあります。白粉のある葉は紫外線を強く反射し、Dudleya属ではUV-Bの83%を反射した例が報告されています(Mulroy, 1979)。毛(トリコーム)も光を散らして葉面の温度上昇を抑えます。これらは遺伝形質で、環境だけで突然消えるわけではありません。ただし触れたり水滴が当たったりすると白粉は剥がれやすく、その部分は日焼けしやすくなります。
斑入りは細胞の一部が葉緑体を持たないためにできる模様で、基本的に遺伝的です。ウイルスによるモザイク斑は不規則で進行性があり、栄養や光では治りません。診断では、「構造が作る色」と「環境が作る色」を混同しないことが重要です。
🏠🌞 室内LEDと屋外日光――運用レンジと順化のコツ
室内LEDでは、徒長を抑えて色を保つためにPPFD 150〜300 µmol m⁻² s⁻¹、点灯12〜14時間でDLI 6〜15を目安にすると扱いやすくなります(Hogewoning et al., 2010; Wollaeger & Runkle, 2015)。青は10〜30%前後、R:FRは1以上(遠赤を強くし過ぎない)の設定が無難です(Franklin, 2008)。UV-Aは発色や徒長抑制に効く場合がありますが、まずは短時間・弱い強度から段階的に試します(Brown & Jenkins, 2008)。
屋外では季節でDLIが大きく変わります。春から初夏にかけて一気に強くなるため、室内越冬株をいきなり直射に出すのは危険です。順化の一例を示します。
- 🗓️ 1週目:終日50%遮光の下で午前だけ日当たりに置く。
- 🗓️ 2週目:30%遮光に切り替え、直射時間を午前〜昼過ぎへ延長。
- 🗓️ 3週目:真夏は30〜50%遮光のまま風を通し、午後の強光は避ける。
この「少しずつ」が、退色や日焼けを防ぐ最大のコツです(Leigh et al., 2006)。
🔎 代表属の着眼点+ミニ診断表
アガベ(Agave)
強光に比較的強い一方、未順化の個体は日焼けしやすいです。春〜初夏は段階的に直射へ移行し、無風時は送風で葉温を抑えます(Nobel, 1988)。白粉がよく乗るタイプは紫外線の反射が強く、順化後は色が安定します(Mulroy, 1979)。
パキポディウム(Pachypodium)
冬の休眠明けは光合成機能が鈍く、急な強光で色抜けしやすい印象があります。点灯時間と距離を調整し、数日単位で明るさを上げると安全です。
ユーフォルビア(Euphorbia, 塊根)
種によって日照の好みが分かれます。赤化はアントシアニン由来と考えて問題なく、夜の冷え込みで色が深まることがあります(Koes et al., 2005)。乳液が出るため、日焼け葉は無理に切らず新葉更新で整える方法も有効です。
| 症状(葉色) | まず疑う原因 | 確かめ方 | 一次対処 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 薄緑で徒長 | 光量不足/青不足/低R:FR | PPFD<100、R:FR<1、節間が長い | PPFDと青を段階的に増やす | (Franklin, 2008; Hogewoning et al., 2010) |
| 黄白に抜ける | 強光への未順化 | 直射・強LEDに替えた直後 | 遮光と送風、順化をやり直す | (Osmond, 1994; Murata et al., 2007) |
| 赤・紫に発色 | 強光・UV・低温(防御反応) | 夜冷え・UVの有無、生育の勢い | 目的に応じ遮光/保温で調整 | (Brown & Jenkins, 2008; Koes et al., 2005) |
| 新葉が鮮やかに黄化 | 鉄欠乏/高pH/過湿 | pH測定、SPAD低下、葉脈間黄化 | キレート鉄、排水改善、pH是正 | (Marschner, 2012; RHS, 2019) |
| 葉縁が褐変 | 日焼け/高葉温 | 葉温>45℃、無風・直射 | 30〜50%遮光と送風 | (Nobel, 1988; Leigh et al., 2006) |
🍀 最後に用土について触れます。黄化や退色には土の通気・排水・pHが密接に関わり、根が健全に呼吸できる構造ほど葉色は安定します(Marschner, 2012)。無機75%・有機25%で、日向土・パーライト・ゼオライトと、ココチップ・ココピートを組み合わせた配合は、過湿を避けつつ保水も確保しやすいため、色の安定に寄与します。詳しくは下記の製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品ページ
光環境関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の光環境完全ガイド【決定版】
参考文献
- Brown, B. A., & Jenkins, G. I. (2008). UV-B signalling pathways with different fluence-rate response profiles. Plant Physiology, 146, 576–588.
- Chalker-Scott, L. (1999). Environmental significance of anthocyanins in plant stress responses. Photochemistry and Photobiology, 70, 1–9.
- Clement, J. S., & Mabry, T. J. (1996). Pigment evolution in the Caryophyllales. Botanical Acta, 109, 360–367.
- Foyer, C. H., Lelandais, M., & Kunert, K. J. (1994). Photooxidative stress in plants. Physiologia Plantarum, 92, 696–717.
- Franklin, K. A. (2008). Shade avoidance. New Phytologist, 179, 930–944.
- Hogewoning, S. W., Trouwborst, G., et al. (2010). The influence of light spectrum on indoor plants. Acta Horticulturae, 907, 141–149.
- Jain, G., & Gould, K. S. (2015). Are betalain pigments the functional homologues of anthocyanins? Environmental and Experimental Botany, 119, 48–53.
- Koes, R., Verweij, W., & Quattrocchio, F. (2005). Flavonoids: regulation and evolution. Trends in Plant Science, 10, 236–242.
- Kovinich, N., Ding, H., et al. (2015). Anthocyanin biosynthesis in Arabidopsis. Plant Physiology, 168, 1036–1046.
- Leigh, A., Sevanto, S., Close, J. D., & Nicotra, A. B. (2006). Leaf size and thermal dynamics. Plant, Cell & Environment, 29, 660–670.
- Marschner, P. (Ed.). (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.
- Mulroy, T. W. (1979). Spectral properties of glaucous leaves in Dudleya. Oecologia, 38, 349–357.
- Murata, N., Takahashi, S., Nishiyama, Y., & Allakhverdiev, S. I. (2007). Photoinhibition of PSII under stress. BBA-Bioenergetics, 1767, 414–421.
- Nobel, P. S. (1988). Environmental Biology of Agaves and Cacti. Cambridge University Press.
- Osmond, C. B. (1994). What is photoinhibition? In Photoinhibition of Photosynthesis. BIOS Scientific.
- Pierik, R., et al. (2009). Auxin and ethylene in elongation under low R:FR. Plant Physiology, 149, 1701–1712.
- RHS (Royal Horticultural Society). (2019). Chlorosis – Causes and Remedies.
- Terry, N., & Ulrich, A. (1974). Phosphorus deficiency and photosynthesis. Plant Physiology, 54, 379–382.
- Wollaeger, H., & Runkle, E. S. (2015). Blue-to-red ratios with LEDs. Acta Horticulturae, 1134, 237–244.
ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認する