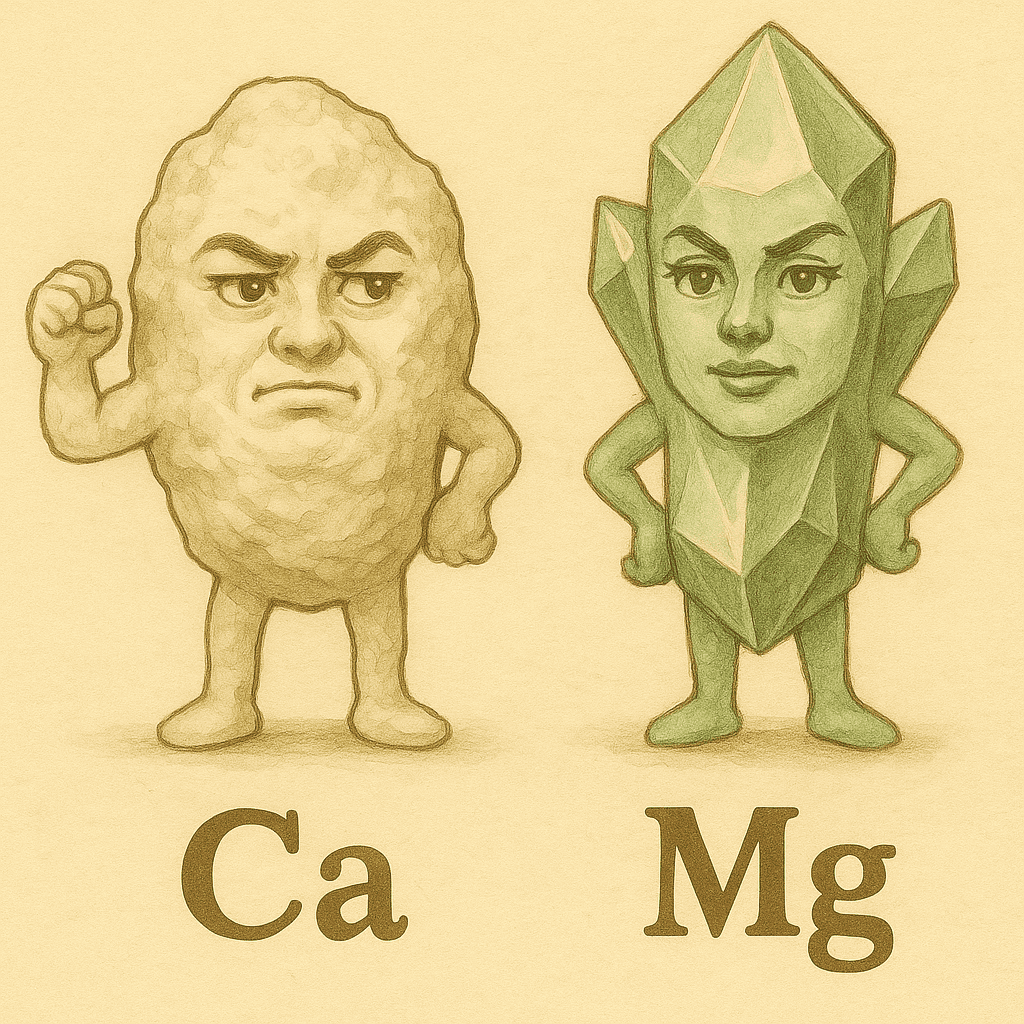🌱 カルシウムとマグネシウムを正しく理解して、美しい株を育てます
塊根植物や多肉植物を健全に育てるには、見落とされがちなカルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg)を押さえることが近道です。カルシウムは細胞壁(細胞の外側を支える壁)の丈夫さをつくり、マグネシウムはクロロフィル(葉緑素)の中心金属として光合成を支えます。本稿では、科学的な裏づけを大切にしつつ解説します。
🧱 カルシウム:新しい葉と生長点を守ります
🔗 何をしている要素か
カルシウムは細胞壁のペクチン(細胞同士をつなぐゼリー状の成分)に結合して、細胞どうしをしっかり接着させます(Hecht-Buchholz, 1979)。この働きによって葉や茎の組織が丈夫になり、葉が裂けにくくなり、病気の侵入口も減ります(Barta & Tibbitts, 2000)。
🚿 欠乏が起きる理由とサイン
カルシウムは植物体内で移動しにくい要素です。そのため根からの供給や葉からの蒸散が滞ると、まず新葉・生長点・幼い果実に症状が出ます。具体的には、新葉では先端が縮れて黒ずみ、葉全体が萎縮して正常に広がらなくなります。生長点では新芽が枯れ込んで停止し、株の成長そのものが止まることがあります。幼い果実では果頂部に黒い陥没や腐れが生じ、形がいびつになる症状として現れます。レタスのチップバーン、トマトの尻腐れ、リンゴのビターピットなどが有名な例です(Adams & Ho, 1993; Barta & Tibbitts, 2000; de Freitas et al., 2015)。鉢栽培では「過湿で風が動かない」「真夏の葉面温度が高すぎて蒸散が乱れる」状況で起きやすいです。
🧭 すぐにできる対処のコツ
まずは環境面を整えます。用土を少し乾かし気味に管理し、サーキュレーターで葉のまわりの空気を動かして蒸散を助けます。カルシウム液肥の葉面散布は有効ですが、「涼しい時間帯・低め濃度・こまめに」が基本です(製品ラベルの下限濃度を目安)。石灰の入れすぎは別の要素(鉄・マンガンなど)の効きにくさを招くことがあるため、様子を見ながら少量ずつが安全です(Marschner, 2012)。
☘️ マグネシウム:葉の“深い緑”と光合成を作ります
🔆 何をしている要素か
マグネシウムはクロロフィル(葉緑素:葉が緑色に見える色素で、光を吸収してエネルギーに変える働きを持つ物質)の中心にある金属で、光合成に欠かせない存在です。さらに、マグネシウムは二酸化炭素を糖に変える酵素や、その他多くの酵素が正しく働くためのサポート役も担います(Cakmak & Kirkby, 2008; Marschner, 2012)。植物体内のマグネシウムの多くはクロロフィルに使われ、残りは養分やエネルギーを利用する反応、タンパク質の合成、葉でつくられた糖を根や茎に運ぶ働きに関与します(Karley & White, 2009)。ここでいう「エネルギーを利用する反応」とは、光合成や呼吸でつくられた力を使って、物質を合成したり細胞内で運んだりする仕組みのことを指します。
🟡 欠乏サインを“見た目”で覚えます
マグネシウムは体内で移動しやすいため、不足するとまず古い葉から症状が出ます。代表例は葉脈間クロロシス(葉脈は緑のまま、間がレモン色に抜ける)です。強い直射や高温が重なると、黄化が早く進み、褐点や壊死が混じることもあります(Cakmak & Kirkby, 2008; Hermans & Verbruggen, 2005)。
🧪 研究の数値を“家庭の目安”に置き換えます
研究では、葉のマグネシウム濃度の適正域や培養液中マグネシウムの濃度が示されています(Hermans & Verbruggen, 2005; Ishfaq et al., 2021)。ただ、家庭栽培でそのまま真似するのは難しいので、次のように置き換えると実務で使いやすいです。
- 葉の黄化が始まったら、エプソム塩(硫酸マグネシウム)を水1Lに1~2g(0.1~0.2%)溶かして、週1回を2~3週与えます。落ち着いたら月1回に戻します(Cakmak & Kirkby, 2008; Marschner, 2012)。
- 葉面散布で使うときは、同じ濃度で夕方に。高温・直射の時間帯は葉焼けリスクが上がるため避けます。
- 長期的には、Mg入り肥料を常用して「切らさない」設計にします。
※ 研究の培養液濃度(たとえば0.5~1.0 mM)は、毎日同じ濃度が循環し続ける前提です。鉢栽培では土に吸着・流出があるため、上の“少し濃いめを間欠で”の方が実務では扱いやすいことが多いです(Ishfaq et al., 2021)。
⚖️ 土壌と用土:pH・CEC・Ca/Mgバランスを“崩さない”
陽イオン交換容量(CEC)は、土がカルシウムやマグネシウムをつかまえて離しにくくする力です。CECが高いと、施したカルシウムやマグネシウムがすぐ流れず、根の近くに残ってくれます。雨の多い酸性環境ではマグネシウムが抜けやすく、逆に石灰岩質ではカルシウムが優位になりがちです。理想は「カルシウムもマグネシウムも不足させない」ことで、比率だけに固執せず両方の絶対量を確保する考え方が実用的です(Mengel et al., 2001; Gransee & Führs, 2013)。 土壌物理の面では、カルシウムが多いと粒子がほどよく凝集して水はけ・通気が良くなり、マグネシウムが多すぎると粒子が分散してベタつきやすくなります。重くなったら石膏(硫酸カルシウム)や有機物の質改善で団粒を戻す、マグネシウム不足なら苦土石灰やエプソム塩で補う、といったシンプルな是正で十分です(Marschner, 2012; Gransee & Führs, 2013)。
🦠 微生物のちから:菌根菌は“見えない根”です
アーバスキュラー菌根菌(AM菌)は、根の外に菌糸ネットワークを広げて「見えない根」を増やし、離れた場所の水と養分を運びます。リンだけでなく、カルシウムやマグネシウムの取り込みを助ける報告もあります(Smith & Read, 2008; Garcia & Zimmermann, 2014)。清潔寄りの用土でも、少量の有機質や健全な通気・水分リズムを保つことで微生物が働きやすい環境になります。
🔍 ぱっと見で判断:Ca欠乏とMg欠乏の見分け表
| 項目 | カルシウム(Ca)欠乏 | マグネシウム(Mg)欠乏 |
|---|---|---|
| 出やすい場所 | 新葉・生長点・幼果(移動しにくい) | 古い葉(移動しやすい) |
| 見た目 | 葉先が縮れ・壊死、成長点が止まる | 葉脈間がレモン色→進むと褐点 |
| 誘因 | 過湿・通風不足・急生長・高温で蒸散乱れ | 長雨や酸性でMg流亡、Ca優位の拮抗 |
| まずの対応 | 風を当てて用土を軽く乾かす、低濃度Ca葉面散布 | エプソム塩1~2g/L、夕方の葉面散布も可 |
| 参考 | (Adams & Ho, 1993; Barta & Tibbitts, 2000; Marschner, 2012) | (Cakmak & Kirkby, 2008; Hermans & Verbruggen, 2005; Ishfaq et al., 2021) |
🌵 品種差の“ほどよい意識”:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア
アガベには石灰岩由来の高カルシウム・高pHでもよく育つ種があり、通風と日射がしっかりあると新葉のトラブルが減りやすい傾向があります。パキポディウムは種によって適正pHの幅が広く、実生は石灰過多で根の動きが鈍ることがあるため慎重に扱う必要があります。ユーフォルビアも産地により反応が分かれるため、基本は「カルシウムを補いつつマグネシウムを切らさない」で、葉色と新芽の張りを見ながら微調整します(Gransee & Führs, 2013; Marschner, 2012)。
🛠️ 日々の運用(最小限のチェックリスト)
💧 水:用土を軽く乾かしてから給水し、通風で蒸散を助けます。
🧪 施肥:N-P-K偏重を避け、カルシウム・マグネシウム入り肥料を選びます。特にマグネシウムが不足した場合は、エプソム塩(硫酸マグネシウム)を水1Lに1~2g溶かして、必要なときに間欠で与えると改善しやすいです。
🌞 環境:葉が黄化したら一度光を弱め、マグネシウムを補給して回復を確認してから光を戻します。
📓 記録:与えた濃度・回数・気温をメモしておくと、再現性が上がり失敗を防ぎやすくなります。
🪴 用土の設計:排水と保肥の“いいとこ取り”にします
カルシウムとマグネシウムは二価陽イオンなので、根の近くに適度に保持しておく設計が向いています。日向土やパーライトで排水・通気を確保し、ゼオライト(二価陽イオンをよく保持する鉱物)とココピート(CECが高い有機繊維)で保肥を補うと、カルシウムやマグネシウムを無駄なく根圏に届けられます(Mumpton, 1999; Marschner, 2012)。植え替え直後は高濃度の追肥を避け、低濃度を回数で分けて与える方が安全に立ち上がります。
📌 まとめ:強い“壁”と深い“緑”を同時にねらいます
カルシウムは新しい組織を守る壁づくり、マグネシウムは光合成を回すエンジンです。蒸散が働く環境を整え、N-P-Kの陰に隠れがちなカルシウム・マグネシウムを切らさず、用土の保肥で根元に留める。この3点を守るだけで、株は締まり、葉色は深く、造形が整います(Adams & Ho, 1993; Cakmak & Kirkby, 2008; Marschner, 2012)。
🛒 PHI BLEND
無機骨格(75%:日向土・パーライト・ゼオライト)で排水・通気を確保し、有機質(25%:ココチップ・ココピート)で保肥を補う配合は、カルシウム・マグネシウムのような二価陽イオンを根の近くに保ちやすい設計です。用土選びで迷ったら、参考例としてPHI BLENDをご覧ください
📚 参考文献
Adams, P. & Ho, L. C. (1993). Effects of environment on the uptake and distribution of calcium in tomato plants. Plant and Soil, 154, 53–58.
Barta, D. J. & Tibbitts, T. W. (2000). Calcium localization and tipburn development in lettuce leaves. Journal of the American Society for Horticultural Science, 125, 294–298.
Cakmak, I. & Kirkby, E. A. (2008). Role of magnesium in carbon partitioning and alleviating photosynthetic damage under stress. Physiologia Plantarum, 133, 692–704.
de Freitas, S. T., McElrone, A. J., Shackel, K. A., & Mitcham, E. J. (2015). Calcium partitioning and allocation and blossom-end rot development in tomato. Journal of Experimental Botany, 62, 2645–2656.
Garcia, G. & Zimmermann, S. (2014). Arbuscular mycorrhizal fungi enhance uptake of calcium and other nutrients in apple seedlings. Scientia Horticulturae, 167, 43–48.
Gransee, A. & Führs, H. (2013). Magnesium mobility in soils as a challenge for analysis and fertilization. Plant and Soil, 368, 5–21.
Hermans, C. & Verbruggen, N. (2005). Physiological characterization of magnesium deficiency in plants. Planta, 220, 633–642.
Ishfaq, M., et al. (2021). Magnesium deficiency affects photosynthesis and nutrient uptake in tomato. Frontiers in Plant Science, 12, 634520.
Karley, A. & White, P. J. (2009). Moving cationic minerals to edible tissues: potassium, magnesium, calcium. Current Opinion in Plant Biology, 12, 291–298.
Marschner, P. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.
Mengel, K., Kirkby, E. A., Kosegarten, H., & Appel, T. (2001). Principles of Plant Nutrition (5th ed.). Springer.
Mumpton, F. A. (1999). La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. PNAS, 96, 3463–3470.
Smith, S. E. & Read, D. J. (2008). Mycorrhizal Symbiosis (3rd ed.). Academic Press.
▶肥料・栄養に関する網羅的な知識はコチラ↓