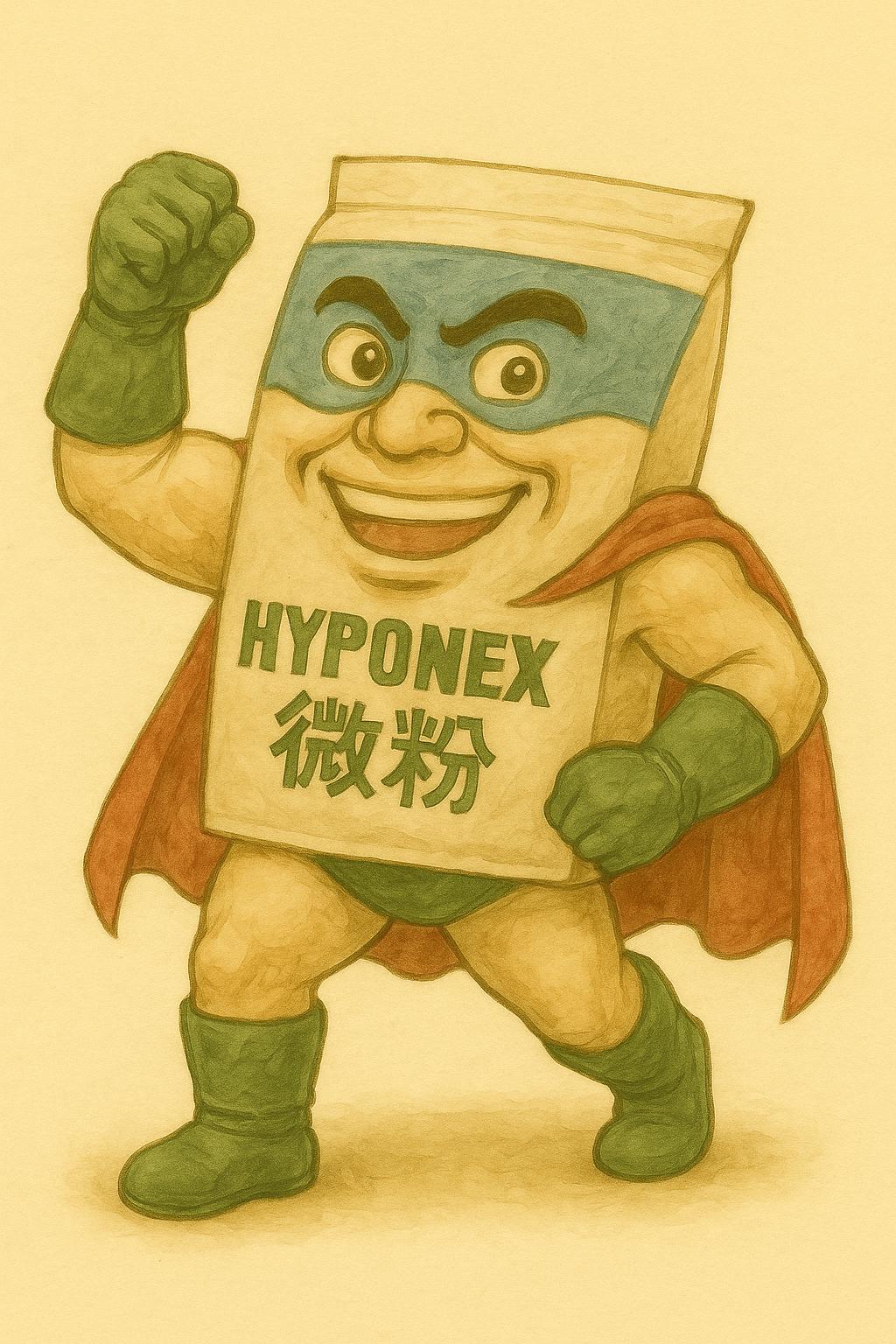塊根・多肉植物育成の観点からみた微粉ハイポネックスの評価と効果的な運用方法
塊根植物や多肉植物を鉢で健やかに、しかも見た目よく大きく育てるには、光・水・温度だけでは満足な結果が得られません。実際のところ、最終的な仕上がりを左右するのは肥料設計です。中でも扱いやすい微粉ハイポネックスは、希釈で濃度を作りやすく、根や葉への立ち上がりも速いので、家庭でも温室でも定番になっています。ただし「これ一つで十分なのか」「ハイポネックス原液と使い分けるべきか」「マグァンプKを基肥にしたほうがよいのか」といった疑問が残ります。本稿では、園芸学・土壌学・植物生理学の知見をベースに、微粉ハイポネックス単独運用の妥当性、有機質を含む培養土と無機主体培養土での運用差、ハイポネックス原液との違いとおすすめの使い分け、そしてマグァンプK併用設計のコツまで、段階的に解説します。
1. 製品プロフィールと出発点:微粉・原液・マグァンプKの立ち位置
はじめに、この記事で扱う三つの製品を概説します。
微粉ハイポネックス(高純度粉末液肥)は、水に溶かして使う即効性の肥料で、保証成分はN–P–K=6.5–6–19(%)です。カリ(K)を多く含み、さらにカルシウムも配合します(Hyponex Japan, 2025)。希釈倍率の目安は植物や生育段階で変わりますが、一般には7~10日に1回の希釈施用が基本になります(Hyponex Japan, 2025)。
ハイポネックス原液(液体肥料)は、水で薄めて使う液状の即効肥料で、保証成分はN–P–K–Mg=6–10–5(%)です。リン酸(P)をやや厚めに含む“山型”の設計で、マグネシウム(Mg)を併せ持つ点が特徴です(Hyponex Japan, 2025)。
マグァンプK(緩効性粒状肥料)は、植え付けや植え替え時に土へ混和する元肥(基肥)で、保証成分はN–P–K–Mg=6–40–6–15(%)です。粒径で効き方が変わり、一般によく使う中粒はおおむね約1年、大粒は約2年、小粒は約2か月効きます。混和量の目安は用土1Lあたり2~8gです(Hyponex Japan, 2025)。
この三者は競合ではなく補完関係にあります。すなわち、微粉/原液=追肥として即効で効かせ、マグァンプK=基肥として持続供給を担う役割分担です。次章から、植物側の要求を科学的に整理し、どの組合せが「綺麗に大きく」に最短距離かを考えます。
2. 多肉・塊根の栄養生理と管理指標:どこを見るべきか
肥料設計の共通言語を先にそろえます。
夜間型光合成(CAM)=「夜に気孔を開いて二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸などに貯め、昼に放出して光合成する方式」です。乾燥地に適応したため水を節約できる一方、塩(肥料)濃度が高いと吸水が鈍りやすい傾向があります(Lüttge, 2004)。
電気伝導度(EC)=「溶液に溶けている肥料塩の総量を間接的に示す指標」です。園芸ではSME法(飽和抽出)・1:2法(用土と水を1:2で抽出)・PourThru法(潅水後に鉢底から出た水を採取)という測り方があり、同じ鉢でも方法で数値が変わる点に注意します(Fisher, 2008)。おおまかに、1:2法はSMEの約半分、PourThruはSMEの約1.5倍の値になります(Greenhouse Management Online, 2008)。
ppm(濃度の単位)=「1リットル当たり何ミリグラムの溶質か」を表します。肥料の窒素濃度(ppm N)は施肥設計の主軸になり、温室栽培の多肉では活着期50~75ppm、育成期50~100ppmが標準的レンジです。培地のEC目標はSME基準で活着期0.8~1.0 dS/m、根が回った後は上限1.8~2.5 dS/mが目安です(Greenhouse Management, 2018)。
また、カリ・カルシウム・マグネシウムの拮抗が重要です。Kが多すぎるとCaとMgの吸収が下がり、Caが多すぎてもMg吸収が落ちます。実務ではK:Ca:Mg ≈ 4:2:1の比率を目安に、過不足やバランス崩れを避けます(e-GRO, 2021)。
3. 希釈→ppm換算:微粉ハイポネックスは何倍で何ppmか
微粉ハイポネックスの窒素は6.5%です。したがって、粉を1.0 g/L(≒1000倍)で溶くと、窒素は約65ppmになります(計算式:1.0g×0.065=0.065g=65mg/L)。リンとカリは日本表記がP2O5・K2Oの酸化物換算であるため、必要なら元素量に換算します(P=P2O5×0.4364、K=K2O×0.8301)。
| 希釈倍率 | 粉量(g/L) | N(ppm) | P2O5(ppm) | K2O(ppm) | P元素(ppm) | K元素(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500倍 | 2.0 | 130 | 120 | 380 | 52.4 | 315.4 |
| 750倍 | 1.333 | 86.7 | 80.0 | 253.3 | 34.9 | 210.3 |
| 1000倍 | 1.0 | 65.0 | 60.0 | 190.0 | 26.2 | 157.7 |
| 1500倍 | 0.667 | 43.3 | 40.0 | 126.7 | 17.5 | 105.0 |
| 2000倍 | 0.5 | 32.5 | 30.0 | 95.0 | 13.1 | 78.9 |
この表から、活着期は1500~2000倍(≒30~45ppm N)、育成期は1000~1500倍(≒43~65ppm N)が、温室基準の安全域に収まることが分かります(Greenhouse Management, 2018)。
4. 培養土が有機か無機かで、運用はどう変わるか
同じ肥料でも、培養土が違うと反応が変わります。ここでは、有機を含む培養土と無機主体の培養土で、設計と管理がどう変わるかを整理します。
4-1. 有機を含む培養土(例:ココチップ+ココピート入り)
有機が含まれると、微生物の働きで窒素の無機化(有機→無機)が起こり、季節や温度で追加の窒素供給が発生します。この「追加分」はコントロールしづらく、冬は止まり、暖かい季節に増えます。そのため、液肥は「やや控えめ」から開始して植物の反応を見ながら増減すると安定します。陽イオン交換容量(CEC)が高まり、KやNH4+を土がつかまえるため、施肥の当たりがマイルドになりますが、同時に塩の在庫もたまりやすくなります。つまり、月1回のリーチング(鉢容積の2倍量の水を流す= ダブルリーチ)で塩を洗い流す手順がより重要になります(Fisher, 2008)。
4-2. 無機主体の培養土(例:日向土・パーライト・ゼオライト主体)
こちらは微生物由来の追加窒素がほぼ無く、CECも控えめで、入れた分だけ効く側に寄ります。濃度設計の再現性は高い一方、潅水のたびに塩が流れ、肥料切れが起こりやすい面があります。したがって、育成期は7~10日に1回の薄め継続施肥が相性よく、活着後はPourThruでのEC確認(SMEの約1.5倍として読む)か、メーターが無ければ月1回のダブルリーチ+症状観察で塩の溜め込みを避けます(Greenhouse Management Online, 2008; Fisher, 2008)。
| 項目 | 有機を含む培養土 | 無機主体の培養土 |
|---|---|---|
| 窒素の追加供給 | 微生物で季節依存の追加あり(春~夏に増える) | ほぼ無し(入れた分だけ効く) |
| CECと当たり方 | CEC高めで当たりがマイルド | CEC低めで反応がダイレクト |
| 肥料切れ | 少なめ(在庫が残る) | 起こりやすい(頻度で補う) |
| 塩の蓄積 | たまりやすい→月1リーチング必須 | 流れやすい→濃度は控えめ継続 |
この差をふまえると、有機混合では薄めから開始して様子見、無機主体では切らさない頻度設計が基本線になります。以降のプロトコルでもこれを前提にします。
5. 微粉ハイポネックス「単独で足りるのか」:長短を科学的に点検する
網羅性の観点では、微粉はN・P・Kに加えてCaと微量要素を含むので、必須要素の多くを供給できます(Hyponex Japan, 2025)。一方、表示にMgが見えにくいため、Mgは水質や基肥で補う設計が安全です(e-GRO, 2024)。
濃度制御の観点では、上の換算表どおり、活着50~75ppm/育成50~100ppmという温室基準を希釈で正確に作れる点が大きな強みです(Greenhouse Management, 2018)。
長期運用のリスクは、①塩類集積、②K過多によるCa・Mgの吸収阻害、③リン供給の持続性です。Kは19%と厚く、連用でK優勢に傾きやすいので、K:Ca:Mg ≈ 4:2:1を意識し、月1のリーチングで塩を逃がします(e-GRO, 2021; Fisher, 2008)。リンは水に溶けた分が土で固定されやすく、沈殿(リン酸カルシウム)がゆっくり再溶解して効きますが、完全な長期安定供給には基肥の援護があると安心です(Hyponex Japan, 2025)。
結論として、短~中期の育成や維持なら単独でも十分に戦えます。ただし、塊根を太らせる長期戦や、超軟水域(Ca/Mgが極端に少ない水)では、後述のマグァンプKを組み込む設計が、安定性と仕上がりの両立に有利です。
6. ハイポネックス原液との違いと使い分け:どちらを選ぶべきか
両者は同社の「追肥」ラインですが、栄養の山の位置が異なります。微粉はK厚め+Ca入り、原液はP厚め+Mg入りです(Hyponex Japan, 2025)。この違いを「狙い」に結び付けると、使い分けが明確になります。
| 項目 | 微粉ハイポネックス(6.5–6–19) | ハイポネックス原液(6–10–5, +Mg) |
|---|---|---|
| 栄養バランス | K厚め+Ca入り(硬く締めやすい) | P厚め+Mg入り(根づくり・葉緑強化) |
| 多肉の相性 | 姿を締めたい、乾き気味管理で強く育てたい | 活着初期、根の再生期、軟水でMgを補いたい |
| 濃度設計 | ppm換算が簡単で細かく刻める | 同様に可能だがPが厚い分、過剰に注意 |
| 注意点 | K過多→Ca/Mg拮抗に注意 | P過多→微量要素の吸収阻害に注意 |
| おすすめ場面 | 育成期の主力/仕上げ期の締め | 発根・植え替え直後/光量が弱い時期 |
多肉・塊根の「綺麗に大きく」という目標では、育成の主力を微粉に置き、活着初期や軟水域では原液を織り交ぜる使い分けが合理的です。どちらも50~100ppm Nの範囲で設計できますが、原液はPが厚いぶん、濃くしすぎると微量要素欠乏(ZnやFe)を誘発しやすくなる点に注意します(Greenhouse Management, 2018)。
7. マグァンプKを基肥にする意味と併用のコツ
マグァンプKは土に混ぜて長く効くため、P(40%)とMg(15%)の基盤供給を安定させられます(Hyponex Japan, 2025)。Pは根づくりとエネルギー代謝の要で、Mgは葉緑素の中心元素です。実際、アガベのnursery試験では、NとPの施肥で葉数・茎径・乾物・根密度が有意に増加し、地上部と地下部の両方が押し上がりました(Sánchez-Mendoza et al., 2022)。
混和量の実務目安は中粒で用土1Lあたり2~4gから始め、植え替え頻度やサイズで最大8g/Lまでの範囲で調整します(Hyponex Japan, 2025)。混和は土全体に均一に行い、固まりを作らないよう気をつけます。置肥として使う場合は、植え付け後3~4週間待ってから与えます(Hyponex Japan, 2025)。
併用の基本形はシンプルです。基肥(マグァンプK)でP・Mgの柱を用土側に置き、追肥(微粉/原液)でNとKを機動的に刻む。これで、K:Ca:Mg ≈ 4:2:1の目安に寄せやすくなります(e-GRO, 2021)。
運用のコツとして、①活着直後は1500~2000倍の薄めから開始、②根が回ったら1000~1500倍へ、③盛夏は吸水が落ちるので頻度を落とす、④月1回はダブルリーチで塩を逃がす、という「濃度×頻度×洗い流し」の三点で組みます(Greenhouse Management, 2018; Fisher, 2008)。
8. 季節・生育段階別プロトコル:有機混合と無機主体での実装
ここからは、家庭で回せる形に落とし込みます。ECメーターが無い場合の代替も併記します。
8-1. 活着前後(春・植え替え直後)
基本設計:マグァンプK中粒を2~4g/L混和。追肥は微粉1500~2000倍(≒30~45ppm N)を10~14日に1回。原液を併用するなら同等のN濃度で、発根が甘い株や軟水域では原液のMgが効きます(Hyponex Japan, 2025)。EC目安はSMEで0.6~1.0 dS/m(Greenhouse Management, 2018)。
有機混合では、無機化の追加Nが乗りやすいので薄め優先で様子を見ます。無機主体では、切らさないため頻度優先で回します。
ECが測れないとき:✅ 白華(鉢縁や受け皿の白い結晶)が出たら即ダブルリーチ。✅ 週1で清水のみ潅水の回を挟むだけでも塩の上振れを抑えられます(Fisher, 2008)。
8-2. 栄養成長(春~初夏・初秋)
基本設計:微粉1000~1500倍(≒43~65ppm N)を7~10日に1回。仕上げを締めたい時期は微粉を主力にし、葉色が淡く伸び悩むなら原液を1回/2~3回の割合で挟み、PとMgを底上げします。EC目安はSMEで0.8~1.5 dS/m(上限1.8~2.5)(Greenhouse Management, 2018)。
有機混合では、夏に向けて微生物活性が上がるため、頻度は維持しつつ濃度を固定して観察を重ねます。無機主体では、濃度を固定し頻度でリズムを作ると、切れと過剰の両方を避けやすくなります。
8-3. 盛夏(高温期)
根の呼吸が鈍り、塊根類は吸水が落ちやすくなります。肥料の吸い込みが悪い時期に濃く入れると、肥料やけになりやすくなります。微粉は1200~2000倍へ緩め、10~14日に1回へ頻度を落とします。原液はP過多に注意し、活着の再建が必要な株に限定して薄めに使います。夕方の涼しい時間帯に施すと安全です。
8-4. 休眠導入(晩秋~冬)
温度低下で生長が止まるため、施肥は基本停止に切り替えます。冬でも動く種類は2000倍を月1以下に留め、白華が見えたらダブルリーチで塩を引かせます。SMEで0.5~0.8 dS/mが一つの目安です(Greenhouse Management, 2018)。
9. 代表属ごとのチューニング:Agave/Pachypodium/Euphorbia
Agave(アガベ)
多くが力強い夏型で、光量・通風・乾きの良さに比例して応えます。nursery条件では、NとPの施肥で葉数・茎径・乾物・根密度が有意に増加しました(Sánchez-Mendoza et al., 2022)。春~初夏は微粉1000倍週1を軸にし、徒長しやすい環境なら1500倍へ緩めて締めます。活着の再建や軟水域では、原液を1~2回に1回の頻度で挟んでMgとPを補います。仕上げ期は微粉比率を上げて葉を厚く締めます。
Pachypodium(パキポディウム)
活着がやや繊細で、盛夏は吸水が落ちやすくなります。高温期は微粉1500~2000倍に緩め、夕方施用を徹底します。原液は発根再建時のみ低濃度で補助し、通常は微粉中心で締めます。植え替え時の基肥は中粒2~4g/Lから開始し、根が回ってから追肥を本格化させます。
Euphorbia(ユーフォルビア)
種類によって性質が分かれ、総じてアガベよりMg不足に敏感です。軟水域や無機主体培土では、マグァンプKをやや厚め(4g/L目安)に入れてMgを底上げすると安定します(e-GRO, 2024)。追肥は微粉1500倍中心で、葉脈間の黄化が出たら原液を一時的に織り交ぜ、Mgを補助します。
10. リスク管理と最終チェック:塩・水質・計測代替
塩類集積(ECの上振れ)は、鉢植え多肉の失速原因の上位です。SMEや1:2、PourThruのいずれかでECを定期確認できれば理想ですが、メーターが無い場合でも、✅ 月1のダブルリーチ、✅ 白華を見たら即洗浄、✅ 週1で清水のみ潅水の回を入れる、といった手当で大部分を防げます(Fisher, 2008)。
水質(硬度・アルカリ度・原水EC)も静かに効きます。アルカリ度が高い水はpHを押し上げ、微量要素欠乏を招きます。実務ではアルカリ度100mg/L(炭酸カルシウム換算)以下を上限目標として扱うことが多く(Penn State Extension, 2023)、高い場合は酸で処理するか、RO水のブレンドで下げます。硬度が極端に低い地域ではCa・Mgが不足しやすいため、基肥のMgと、必要に応じCaの葉面補給を検討します(UF/IFAS, 2019)。
K:Ca:Mgの拮抗は、迷ったら原則の4:2:1に立ち返ります。微粉はKが厚く、原液はMgを含みます。基肥(マグァンプK)のMgと合わせ、総量で4:2:1に近づくように配合を調整すると、欠乏や過剰の事故が激減します(e-GRO, 2021)。
最後に、記事の内容をそのまま点検リストにします。🧪チェックリスト:成分表記(P2O5/K2Oか元素か)を確認(Hyponex Japan, 2025)/希釈→ppm計算を一度紙に書き出す/活着と育成の濃度を切り替える(Greenhouse Management, 2018)/月1でダブルリーチ(Fisher, 2008)/水道の硬度・アルカリ度の概数を把握(UF/IFAS, 2019; Penn State Extension, 2023)/K:Ca:Mgを概算して4:2:1に寄せる(e-GRO, 2021)。
以上を守れば、微粉ハイポネックス単独でも十分に整った育成が可能になり、さらにマグァンプKを基肥に組み合わせることで、塊根を太らせながら姿を崩さない一貫した生長ラインに乗せられます。通気・排水・清潔性の高い用土は、この運用を実装しやすくします。無機質75%・有機質25%で、日向土・パーライト・ゼオライトとココチップ・ココピートを骨格にした配合は、濃度の当たり外れを小さくし、リーチングでの塩抜きも容易にします。詳細は下記をご参照ください。
👉 PHI BLEND 製品ページ
参考文献
e-GRO(2021). Nutrient antagonisms: Potassium, Calcium, and Magnesium(K:Ca:Mg ≈ 4:2:1 の実務目安)。
e-GRO(2024). Magnificent Magnesium(Mg不足の発生機序と対策)。
Fisher, P.(2008). Use the 1:2 testing method for media pH and EC. Greenhouse Management(1:2法とSME/PourThruの関係)。
Greenhouse Management(2018). Succulents – A How-To Production Guide(多肉のppm N=50–100、SME ECレンジ)。
Greenhouse Management Online(2008). Mineral Nutrition – Extraction Methods(PourThruはSMEの約1.5倍、1:2は約1/2)。
Hyponex Japan(2025). 微粉ハイポネックス製品情報(N–P–K=6.5–6–19、Ca入り、希釈と使用法)。
Hyponex Japan(2025). ハイポネックス原液製品情報(N–P–K–Mg=6–10–5、“山型”、15種微量要素)。
Hyponex Japan(2025). マグァンプK製品情報(N–P–K–Mg=6–40–6–15、中粒の有効期間と用土1Lあたり2~8g)。
Lüttge, U.(2004). Ecophysiology of Crassulacean Acid Metabolism(CAM). Annals of Botany 93: 629–652(CAMの環境応答)。
Penn State Extension(2023). A Water Quality Toolkit for Greenhouse and Nursery Production(アルカリ度上限の目安)。
UF/IFAS(2019). Water Quality Notes: Alkalinity and Hardness(硬度・アルカリ度の基礎)。
Sánchez-Mendoza, A., Bautista-Aparicio, G., Bautista-Cruz, A.(2022). Inorganic fertilization improves Agave potatorum growth and nutrition. International Journal of Agriculture and Natural Resources 49(3): 147–156.
▶肥料・栄養に関する網羅的な知識はコチラ↓