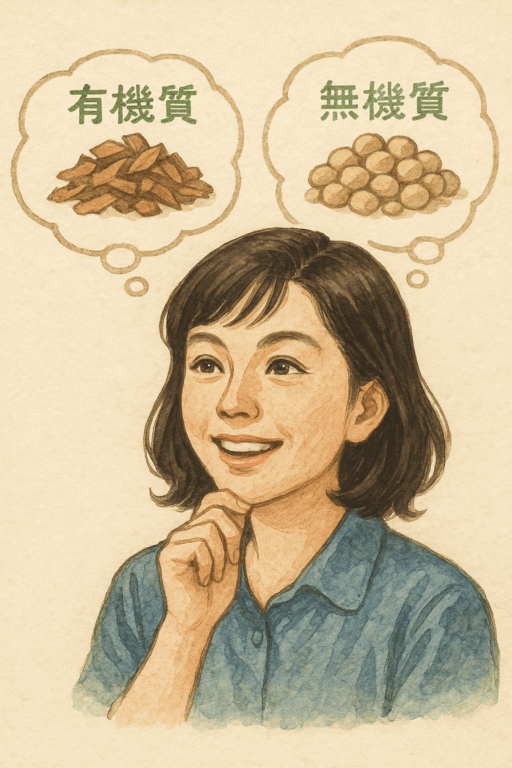🪴 無機と有機の役割と相互作用──塊根・多肉植物の培養土設計の要点
塊根植物や多肉植物を綺麗に大きく育てるには、鉢の中で起きている物理・化学・生物の現象を正しく捉え、無機資材(鉱物由来で分解しにくい素材)と有機資材(植物由来で徐々に分解する素材)を意図通りに配合することが重要です科学的根拠に基づいて無機と有機の観点から培養土設計の実務指針を提示します。
⚖️ 1. 用土の二本柱:無機資材と有機資材
🔍 1-1. 定義の確認と本稿での使い分け
無機資材とは、赤玉土・日向土・軽石・パーライト・ゼオライトなど、鉱物由来で生物分解をほぼ受けない素材の総称です。主な役割は通気・排水・構造安定です。一方の有機資材は、ココピートやココチップ、ピートモス、バークなど、炭素を含む生物起源の素材で、時間とともに分解します。主な役割は保水・保肥(陽イオン交換)・微生物相の維持です(Verdonck & Gabriëls, 1988; Raviv & Lieth, 2008)。
⚖️ 1-2. 「混ぜる理由」──相反する性質を揃えて活かす
無機は乾きやすく酸素を供給しますが、水と養分をつなぎとめる力(CEC)に乏しい素材が多い対照で、有機は保持力に優れる半面、量や粒度を誤ると過湿や病原菌優占の温床になり得ます。両者を混ぜる目的は、空気(通気)と水(保水)の「ちょうどよい両立」を、鉢という閉鎖系で実現するためです(Raviv & Lieth, 2008)。
🌬️ 2. 物理設計:通気・排水・保水のバランス
💨 2-1. 空気充填率(AFP)の考え方
空気充填率(AFP)は「潅水直後に用土中の空気が占める割合(%)」で、根の呼吸に直結します。古典的基準では、AFPが20%前後以上であれば健全な根の好気呼吸が維持されるとされます(Verdonck & Gabriëls, 1988; Raviv & Lieth, 2008)。無機粗粒を主体にするとAFPを確保しやすく、細粒・繊維が多いとAFPは下がります。
💧 2-2. 毛管現象と粒径分布の設計
毛管現象は「細い孔が水を引き上げ保持する」現象です。大粒(軽石・日向土4–6mm)は重力排水を促し、微粒(ココピート等)は毛管で水を抱えます。混合すれば、大孔隙で通気を維持しつつ、微細孔で可給水分(植物が使える中間水分)を確保できます(Raviv & Lieth, 2008)。
📌 2-3. 代表素材の物理要約
🪨 日向土・軽石:多孔質で排水性・通気性に優れる。内部微細孔がわずかな保水も担う。
🫧 パーライト:極めて軽量。粒間空隙が大きく水が滞留しにくい。長期で粉化するため粒度選定が重要。
🧵 ココピート:繊維由来の細孔で高い水分保持(乾物重の数倍)と再湿潤性(Prasad, 1997)。
🪵 ココチップ:粗大繊維片で通気骨材として働き、過度の保水を避けつつ緩やかに水膜を残す。
🧪 3. 化学設計:CECとpH緩衝、塩類管理
🧲 3-1. 陽イオン交換容量(CEC)と肥効の持続
CECは「肥料の陽イオン(K⁺、NH₄⁺、Ca²⁺など)をつかまえて離しにくくする力」です。ココピートは一般に60–120 cmol(+)/kgと高く(Prasad, 1997)、施肥のピーク濃度を和らげます。一方、多くの無機粒(パーライト・軽石)はCECが低いですが、ゼオライトは例外的に高CECでアンモニウムを選択吸着し、肥効の緩衝・緩効化に寄与します(Mumpton, 1999; Sangeetha & Baskar, 2016)。
🧷 3-2. pH緩衝とキレート作用
有機物中の腐植質(フミン酸・フルボ酸)は酸性官能基によりpH変動を緩衝し、鉄などの微量要素を可溶化(キレート)して欠乏を抑えます(Canellas et al., 2014)。無機側では、ゼオライトや一部の焼成クレーが、用土酸性化を抑える酸緩衝に働く場合があります(Mumpton, 1999)。
🧂 3-3. 塩類集積(EC上昇)のコントロール
鉢は排水・土量が限られるため、化成肥料の使い方次第でEC(電気伝導率)が上がりやすく、根の浸透圧ストレスを招きます。高CECの有機(ココピート)やゼオライトを混ぜると、溶液中の急上昇を抑えやすくなります(Prasad, 1997; Mumpton, 1999)。いずれにせよ、薄めの施肥+定期的なリーチング(洗い流し)が芯となる管理です。
🧫 4. 生物設計:微生物相と病原リスクの均衡
🧫 4-1. 微生物活性はどこまで必要か
有機を混ぜると微生物が活性化し、呼吸(二酸化炭素放出)や養分循環が高まります。ピートを減らした代替培地でも、ココ・バーク・無機素材の組合せによって微生物活性が有意に変わることが示されています(Van Gerrewey et al., 2020)。「少量の有機+通気の確保」は、多肉にとって好都合な緩やかな肥効と病害の抑制を両立しやすい構えです。
🦠 4-2. 病原菌(Pythium・Phytophthora)と過湿の関係
過湿や停滞水は卵菌類(Pythium・Phytophthora)を利し、根腐れを引き起こします。観葉・花卉の報告でも、水系を介する病原拡散が繰り返し指摘されており(Stanghellini & Rasmussen, 1994)、カランコエの例でも両属の関与が検出されています(Watanabe et al., 2007)。通気の確保と水停滞の回避は、病原圧の低減策として最優先です。
⚗️ 5. 化成肥料×用土の相互作用(無機主体と有機主体)
🎛️ 5-1. 無機主体での化成肥料:制御性と「濃度ピーク」
無機主体(土自体はほぼ無養分・低CEC)では、化成肥料の投入がそのまま濃度ピークとして根に現れやすく、ECスパイクやpH変動がダイレクトに効きます。一方で、養分のオン・オフを設計的に制御しやすい利点もあります。過剰の兆しがあれば洗い流してリセットし、希薄濃度の継続施肥に戻す戦略が適します(Raviv & Lieth, 2008)。
🍃 5-2. 有機主体での化成肥料:緩衝と「微生物の一時保管」
有機主体(高CEC)では、腐植やココの表面で肥料イオンが一時吸着され、微生物への一時固定→鉱化という緩やかな供給サイクルが働きます(Canellas et al., 2014; Van Gerrewey et al., 2020)。濃度ピークは緩くなりますが、過湿化+高窒素の条件では嫌気・ガス発生のリスクが上がるため、物理性の劣化(目詰まり)を感じたら植え替え更新を選びます。
📦 6. 資材別プロファイル(PHI BLEND構成素材を中心に)
🧱 6-1. 無機:日向土・パーライト・ゼオライト
🪨 日向土:火山性多孔体で排水・通気に優れ、粒形が崩れにくい。CECは低い。
🫧 パーライト:極軽量で通気寄与が大きいが、粉化や浮き上がりがあるため粒度と混合率の最適化が鍵。
🧲 ゼオライト:高いCECと選択性でアンモニウム・カリウムを保持し、肥効の緩衝材として働く(Mumpton, 1999; Sangeetha & Baskar, 2016)。
🌴 6-2. 有機:ココピート・ココチップ
🧵 ココピート:保水・再湿潤性に優れ、CECも高い(Prasad, 1997)。近年の製品はCa/Mgバッファ済みで初期塩の懸念が低い。
🪵 ココチップ:粗大繊維による通気骨格。水持ちし過ぎず、乾き過ぎも緩和。チップの粒度で乾き方を調整できる(Machado et al., 2021)。
🧩 7. 75:25という設計値——PHI BLENDの理屈と運用
🧩 7-1. 理屈:通気の土台(75%)に、保水・保肥の薄い膜(25%)を重ねる
無機75%:有機25%は、潅水直後のAFPを確保しつつ、可給水分を薄く広く保持する設計値です。通気・排水は日向土+パーライトが担い、保水・保肥・緩衝はココピート+ココチップが受け持ちます。ゼオライトが肥料タンクとしてピーク濃度を抑え、施肥を扱いやすくします(Verdonck & Gabriëls, 1988; Mumpton, 1999)。
🔧 7-2. 運用:季節・環境・鉢サイズで微調整
🔧 乾きが速すぎるとき:ココピートの比率や微粒(1–2mm級)を+5〜10%増やす。
🔧 乾きが遅いとき:チップを粗く、パーライト比率を+5〜10%上げる。
🔧 肥料管理が難しいとき:ゼオライトを+5%ほど補強してCECを底上げする。
これらはAFPを20%前後以上に保ちながら、可給水分帯域を狙い撃ちする調整です(Raviv & Lieth, 2008)。
🌿 8. 品種差への翻訳(アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア)
🌵 8-1. アガベ(Agave)
ロゼット内の保水構造が強く、根は高AFP(通気優位)で健全に伸びます。PHI BLEND標準で、夏季の強日照・高蒸散環境ではパーライトや粗チップの比率をわずかに上げると、徒長や根部の酸欠を避けやすくなります。
🌱 8-2. パキポディウム(Pachypodium)
太い塊根は過湿に敏感ですが、初夏の勢いがつく局面では水の取り逃しを避ける必要があります。標準配合から微粒の有機(ココピート)を5%だけ加えると、潅水間隔の安定化に寄与します。
🪴 8-3. ユーフォルビア(Euphorbia)
種類による差が大きく、総じて滞水を嫌う一方、細根型の種では表層の乾き過ぎに弱い個体もあります。表土だけ微粒を厚さ1cm程度敷く、あるいはゼオライトを微量追加して可給水分を補うと安定しやすくなります。
🧭 9. 現場での判断基準(再現性を高めるために)
⚖️ 9-1. 重量法と乾き時間
鉢を潅水直後・完全乾燥時に持ち比べ、手の記憶で中間重量を掴みます。自分の環境で何日で乾くかを季節ごとに記録し、狙いの乾き日数に対して配合や粒度を微調整します。
👀 9-2. 見た目サインと根の色
表土の色変化(湿時は濃く、乾くと淡い)、株の張り、下葉の色、鉢底から見える根の色(健康な根は白〜淡褐色)を合わせて判断します。黒ずみや嫌気臭を感じたら、AFP不足=過湿のサインです。
🧂 9-3. 塩類管理(EC・洗浄)
希薄な液肥を定期で与え、月1回は鉢底から十分に水を出す洗浄潅水でECの蓄積をリセットします。ココ系を初めて使う場合は、導入初期に2–3回の慣らし潅水を行い、不要塩の初期溶出を促します(Prasad, 1997; Mumpton, 1999)。
🧾 10. まとめと次の一歩
無機と有機には明確な役割分担があります。無機は通気と骨格、有機は水と養分の緩衝。両者を75:25程度で組み合わせると、塊根・多肉にとって過湿と過乾の双方を避けつつ、肥料の効きを穏やかに保つ鉢内環境を作れます。病原リスクの観点からも、通気の維持(AFP確保)と滞水回避は最優先であり、配合比と粒度設計で物理性を先に固め、CECやpH緩衝で化学性を「微修正」する順序が再現性を高めます(Verdonck & Gabriëls, 1988; Raviv & Lieth, 2008; Van Gerrewey et al., 2020)。
🧪 製品のご案内
本稿の設計思想に基づく配合として、PHI BLEND(無機75%・有機25%:日向土/パーライト/ゼオライト+ココピート/ココチップ)をご用意しています。配合詳細は下記でご確認ください。
PHI BLEND 製品ページへ
用土全般の整理はこちら
📚 参考文献
※本文中の括弧内は著者・年を示します。原典の所在は以下。
- Canellas, L. P., Olivares, F. L., et al. (2014). Physiological responses to humic substances as plant growth promoters. CHEMI (Open Access). DOIなし(Web記事)。
- Carlile, W. R., et al. (2015). Organic Growing Media: Constituents and Properties. Vadose Zone Journal, 14(6).
- Machado, R. M. A., et al. (2021). Coir, an Alternative to Peat—Effects on Plant Growth and Substrate. Horticulturae, 7(6):127.
- Mumpton, F. A. (1999). La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. PNAS, 96(7):3463–3470.
- Prasad, M. (1997). Physical, chemical and biological properties of coir dust. Acta Horticulturae, 450:21–30.
- Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008/2018). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier(第2版)。
- Sangeetha, C., & Baskar, P. (2016). Zeolite and its potential uses in agriculture: A review. CABI Digital Library(資料)。
- Stanghellini, M. E., & Rasmussen, S. L. (1994). Hydroponics: A solution for zoosporic pathogens. Plant Disease, 78:1129–1138.
- Van Gerrewey, T., et al. (2020). Microbial activity in peat-reduced plant growing media. Journal of Cleaner Production, 256:120323.
- Verdonck, O., & Gabriëls, R. (1988). Substrate requirements for plants. Acta Horticulturae, 221:19–23.
- Watanabe, H., Taguchi, Y., Hyakumachi, M., & Kageyama, K. (2007). Pythium and Phytophthora species associated with root and stem rots of kalanchoe. J. General Plant Pathology, 73:81–88.
- Soul Soil Station (2025). 「有機用土と化成肥料の相性」記事(統合元)。URLは当サイト内。
- Soul Soil Station (2025). 「無機質と有機質、用土におけるそれぞれの役割と違い」記事(統合元)。URLは当サイト内。
🗂️ 用語ミニ辞書
※初出時の定義を再掲します。
- 無機資材:鉱物由来で分解されにくい素材(軽石・日向土・パーライト・ゼオライト等)。
- 有機資材:植物由来で徐々に分解する素材(ココピート・ココチップ・ピート・バーク等)。
- 空気充填率(AFP):潅水直後に用土が保持する空気の割合(%)。20%前後以上が目安。
- 毛管現象:細孔が水を引き上げ保持する現象。微粒ほど毛管力が強い。
- CEC(陽イオン交換容量):肥料イオンを保持する力。高いほど肥効が緩やかに続く。
- 腐植質:フミン酸・フルボ酸などの有機高分子。pH緩衝とキレート作用をもつ。
- EC(電気伝導率):溶液中の塩類濃度の指標。上がり過ぎは根の浸透圧ストレス。
- リーチング(洗浄潅水):溜まった塩類を水で洗い流す管理操作。
- 可給水分:植物が吸える中間水分。粗大孔では保持されず微細孔で保持されやすい。
- 卵菌類:PythiumやPhytophthoraなど。水系で拡散しやすく過湿で優占。