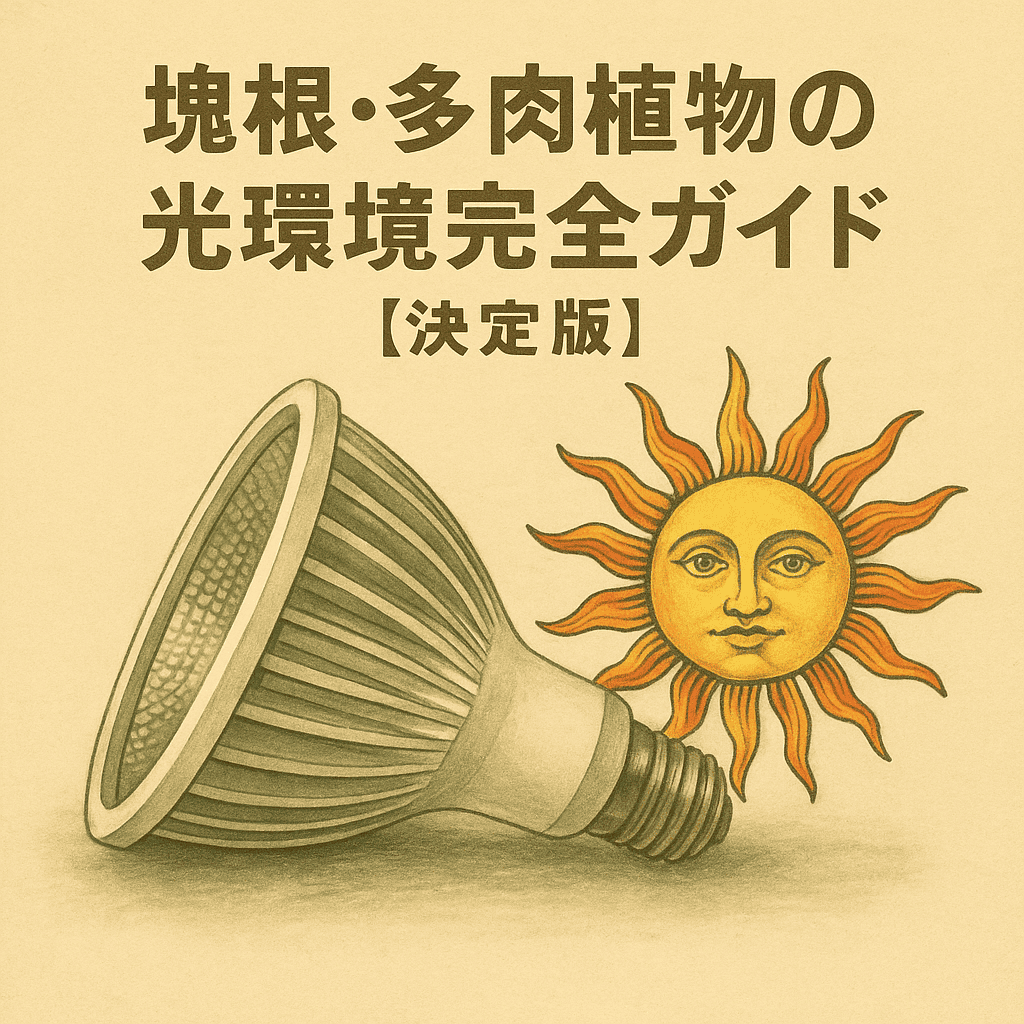
光環境総論:PPFD・DLI・光質で考える徒長防止
🌞塊根植物や多肉植物は、形と密度の美しさが命です。その「締まった姿」を決める主役は水や肥料ではなく、まず光です。本稿では、徒長(茎や葉が間延びしてしまう現象)を避けながら「綺麗に大きく育てる」ために、家庭栽培でも実行できる光設計の考え方を、科学的根拠に基づいて整理します。専門用語を可能な限り園芸の言葉に置き換え、数式は噛み砕いて説明します。最後に、強い光環境に耐え、根を健康に保つための用土設計にも触れます。
1. 光の指標をひとつずつ押さえる(PPFD・DLI・光質)
🔦まず前提となる用語を、最初に簡潔に整理します。
・PPFD(光の強さ):1秒あたり、1平方メートルの葉に当たる光の粒(光合成に使える光子)の数を表します。単位は「µmol/m²/s」です。数が大きいほど瞬間的な明るさが強いことを意味します。
・DLI(1日の光の合計):1日で受けた光の合計量です。単位は「mol/m²/日」です。計算は「平均PPFD × 日照または点灯時間(秒) ÷ 1,000,000」で行います(Runkle & Both, 2017)。瞬間の明るさだけでなく、合計の「稼ぎ」を見るために使います。
・PAR(光合成に使える波長域):従来は400〜700ナノメートルの範囲を指しました。最近は赤のやや外側(700〜750ナノ)も条件により同等に働くとする見解があり、これをePARと呼びます(Zhen & Bugbee, 2020)。
・R:FR(赤と遠赤の比):赤色付近(おおよそ660ナノ)と遠赤色付近(おおよそ730ナノ)の比率です。これが低い(遠赤が多い)と、植物は「日陰にいる」と判断し、間延びしやすくなります(Casal, 2013)。
・PSS(フィトクロムの光定常状態):植物内の光センサーであるフィトクロムが「赤い光」と「遠赤の光」をどのような割合で受け取っているかを数値にしたものです。植物が「今いる環境を日向と感じているのか、日陰と感じているのか」を示す目安だと考えると分かりやすいでしょう。例えば、太陽の直射光では赤い光が十分にあるためPSSの値は高くなり、植物は「日向だ」と認識します。一方、森の木陰や群落の中では遠赤の割合が増えるためPSSは低くなり、「日陰にいる」と判断して茎を伸ばす反応が強まりやすくなります。(Franklin & Quail, 2010)。
・拡散光:雲やレースカーテン、白壁の反射などで、方向がバラけた柔らかい光です。直射に比べて葉焼けしにくく、葉の裏や株元まで光が回りやすい利点があります(Hemming et al., 2008; Li et al., 2014)。
・徒長:光不足や光質の偏りで、節と節の間が伸び、葉が薄く、株の輪郭がぼやける症状です。園芸上の見た目だけでなく、光合成器官の密度が下がり、将来の生育にも不利に働きます(Yang & Li, 2017)。
2. 徒長はなぜ起きるのか(生理の要点)
📈徒長は単なる「光が弱い」の一言で片づけられません。植物は赤と遠赤の比(R:FR)やPSS、そして光の総量(DLI)から、周囲の環境を読み取ります。周囲に他の植物があると、葉に当たる光は遠赤が増え、R:FRが下がります。すると体内の光センサー(フィトクロム)が「日陰回避」のスイッチを入れ、オーキシンやジベレリンなどのホルモンを介して節間を伸ばし、葉を上向きに傾ける行動に移ります(Franklin & Quail, 2010; Yang & Li, 2017)。これが日陰回避応答(Shade Avoidance)です。塊根・多肉でも基本の仕組みは同じで、低PPFDや低DLI、低R:FR(遠赤が多い)では徒長を誘発しやすくなります(Casal, 2013)。
🔬一方で、青色の成分は、別の光センサー(クリプトクロムやフォトトロピン)を通して、葉や茎を締める方向に働くことが多く報告されています。赤単独に青を少し混ぜるだけで、節間が詰まり、葉厚や色の引き締まりが改善する例が温室作物で繰り返し観察されています(Kaiser et al., 2019)。ただし青だけに偏らせ過ぎると成長効率が落ちたり、種によっては逆の反応を示す場合もあるため、バランスが重要です(Kong & Zheng, 2024)。
関連リンク:徒長の原因と予防法:光・水・温度を科学的に分析
3. どれくらいの明るさが必要か(PPFD・DLIの現実的レンジ)
🌿原生地の強い日射に適応してきた塊根植物や多肉植物は、家庭でもある程度の「強さ」と「合計量」が必要です。ここでは代表的な属ごとに、成株・若株・実生の段階別に目安をまとめます。過剰光と不足のサインを観察しながら、無理のない範囲で調整していきましょう。
🌵 アガベ属(多くはCAM型)
アガベは典型的な強光性植物で、成株ではPPFD 500〜800 µmol/m²/s、DLI 20〜30 mol/m²/日が目安です。青の割合は10〜20%が締まりやすく、R:FRは1.1以上を維持するのが理想です。若株は300〜500 µmol/m²/s程度に抑え、葉焼けを避けながら慣光します。実生では150〜300 µmol/m²/sが安全域で、遠赤を減らして間延びを防ぎましょう。
光が弱いと葉が薄く長くなり、色が淡くなります。逆に強すぎると葉先の褐変や白化が見られます。
🌳 パキポディウム属(塊根木)
パキポディウムはやや柔軟で、成株ではPPFD 400〜700 µmol/m²/s、DLI 18〜25 mol/m²/日が安定します。青光は10〜15%で十分締まり、遠赤を控えると徒長を防げます。若株では250〜400 µmol/m²/s前後が適切です。実生は根が張るまでは100〜200 µmol/m²/s程度の穏やかな光で管理します。
光不足では葉が薄く下垂し、節間が間延びします。強光下では表皮の斑点やコルク化が出るため、春の慣光を丁寧に行いましょう。
🌿 ユーフォルビア属(多肉型)
ユーフォルビアの多肉型種も明るい環境を好みます。成株でPPFD 400〜600 µmol/m²/s、DLI 15〜25 mol/m²/日が適量です。青光は10〜15%、R:FRは太陽光相当を意識します。若株では250〜400 µmol/m²/sで十分で、遠赤を抑えると茎の締まりが良くなります。実生は100〜150 µmol/m²/sを上限に、光不足で倒伏しないよう注意します。
強光では茎表面が褐変することがあり、遮光ネットや拡散光を活用すると安定します。
🍃 斑入り個体(共通補正)
斑入り品種は葉緑素が少ないため、耐光性が通常株より低くなります。光量は上記レンジより20%ほど下げて開始し、段階的に慣らすと安全です。白斑部が焼けやすく、葉の黄化や透けが見られたら光が強すぎるサインです。反対に暗すぎると黄緑化し徒長するため、明るい半日陰〜柔らかい補光でバランスを取ります。
🧭これらの数値は「出発点」であり、最適値は環境や品種によって変わります。株の反応(葉の厚み・色・節間の詰まり)を観察しながら、少しずつ距離や照射時間を調整してください。特に実生と斑入りは過剰光に敏感なため、焦らず「段階的な慣光」を徹底することが健全な育成への近道です。
関連リンク:光合成に必要な光の質と量とは?
関連リンク:日焼け(葉焼け・幹焼け)を防ぐ遮光設計
4. 光の「質」を設計する(青・赤・遠赤・UVの使いどころ)
💡青の配合は「締めるノブ」として使います。赤主体の光に対して青を10〜20%程度混ぜると、節間が詰まり、葉が厚くなる傾向が多くの作物で見られます(Kaiser et al., 2019)。ただし青ばかりにすると光合成効率が下がる例や、種によっては伸長が誘発される例もあるため、青10〜20%を起点に、株の反応で微調整します(Kong & Zheng, 2024)。
🌗遠赤は「伸ばすノブ」になりがちです。遠赤が増えてR:FRが低下すると、フィトクロムを介した日陰回避が働き、徒長を招きやすくなります(Casal, 2013; Franklin & Quail, 2010)。一方で、遠赤は葉の奥まで光を通しやすく、赤+遠赤+他の波長がそろう条件では光合成に寄与するという知見もあり(Zhen & Bugbee, 2020)、全否定はできません。家庭栽培ではR:FRが不自然に低くならないよう(極端な遠赤強調LEDを避ける、照明を植物に近づけ過ぎない等)配慮し、必要なときにごく少量を使うくらいの設計が無難です。
🛡️UV-A/UV-Bは「締まりと色づきのスパイス」になり得ます。適度なUVは表皮の防御反応を促し、アントシアニンなどの色素合成を高めて葉の色合いと耐日射性を改善します(Jenkins, 2017)。ただしUV-Bは生体への負荷も大きいため、弱く・短く・段階的に導入します。一般的な住宅用ガラスはUV-Bを大きく減衰させるため、屋外管理では自然にUVを得られ、室内では不足しがちです(Levinson et al., 2010)。
関連リンク:葉が赤~紫になる原因と対処方法
5. 室内でDLIを稼ぐ(窓・拡散・反射・方位の実務)
🏠家庭の窓辺は、外の直射日光に比べて光が弱くなりがちです。ガラス・網戸・レースカーテン・室内の遮蔽物で光は減衰し、さらに壁や床の反射率によっても株に届く光が変わります。住宅用の透明ガラスは可視域で高い透過率を持ちますが、設置条件や角度で実効的な透過率は下がります(Levinson et al., 2010)。このため、室内だけで多肉のDLIを十分に確保するのは難しく感じられるかもしれません。
🌥️ここで役立つのが拡散と反射の考え方です。直射は強いものの当たり方が偏ります。これに対して、拡散光は株全体に回り込み、葉裏や株元の光合成も助けます(Hemming et al., 2008; Li et al., 2014)。窓際で背景を白くする(白い壁・白のボード・光沢紙)だけでも、株に返ってくる光が増えます。レフ板やアルミ蒸着の反射シートを鉢の背面や側面に置くと、影側の葉にも光を届けられます。レースカーテンは過剰な直射をやわらげる一方で、過度に厚い布はPPFDを落とし過ぎるため、季節と時間帯で使い分けます。南向きは冬の味方、東向きは朝の光で締まりやすく、西向きは夏の高温とセットになりやすいので注意します(Hemming et al., 2008)。
関連リンク:DLI(1日の光量)を家の窓辺だけで確保することは可能か?
6. 計測と換算:見える化が最短の近道
📏光は「見た目の明るさ」と「植物の感じる明るさ」が一致しません。人の目の明るさ(ルクス)は緑色に敏感ですが、植物は赤や青も等しく数えます。量子センサー(PARセンサー)があれば最も確実です(Runkle & Both, 2017)。一方、最近はスマートフォンのアプリでも、拡散板を組み合わせることでPPFDやDLIを概算できるものがあります。スマホ計測は±10〜20%程度の誤差を見込んだうえで、同じ場所・同じ姿勢で繰り返し測り、値の傾向で判断します(Apogee Instruments, 2021)。
🧮DLIの式は簡単です。「DLI = 平均PPFD × 点灯(または日照)時間(秒) ÷ 1,000,000」です(Runkle & Both, 2017)。例えば、平均400µmol/m²/sの光を10時間当てれば、DLIは約14.4 mol/m²/日になります。断続的に照らす場合も、積分(足し算)で同じだけ稼げば同じDLIになります。
💡ルクス→PPFD換算は光の色によって係数が変わるため注意が必要です。太陽光や白色LEDでは「1µmol/m²/s ≈ 50〜70ルクス」程度の目安が使われますが、赤/青に偏った光では大きく外れます(Apogee Instruments, 2021)。スマホの照度(ルクス)しか測れない場合は、まず白色光かどうかを確認し、複数点で測って平均をとり、換算は幅をもって扱います。
関連リンク:PPFDの測り方:スマホ計測と誤差補正
7. LED運用:出力・距離・タイマーの初期設定
🔧LEDを室内補光に使うと、DLIの不足分を狙って埋められます。設置のコツは次の3点です。第一に、距離です。光は距離の二乗に反比例して弱くなるため(いわゆる逆二乗則)、距離を半分にするとおおよそ4倍のPPFDになります(Nelson & Bugbee, 2014)。焦げそうなら離し、徒長しそうなら近づけます。第二に、青の割合です。赤主体に青を10〜20%程度混ぜた光で、まずは形を締めます(Kaiser et al., 2019)。第三に、点灯時間です。家庭では12〜14時間の一定点灯でDLIを積み増す運用が扱いやすく、季節に応じて±2時間の微調整を行います(Runkle & Both, 2017)。
🗺️同じ器具でも、中心と周縁でPPFDが大きく違います。設置後に株の位置ごとに測り、簡易のPPFDマップを作ると、徒長しやすい周縁の株を中心に寄せる、反射板を追加する、といった改善が進みます。複数灯を低めに分散配置すると、1灯を高出力で高く吊るより均一な明るさを得やすく、徒長ムラを抑えられます(Hemming et al., 2008)。
関連記事:LEDライトの波長と育成効果の関係
8. 光×温度・水・栄養のバランスを揃える
🌬️強い光は、同時に葉温の上昇と蒸散の増加を招きます。水が足りなければ気孔が閉じて二酸化炭素の取り込みが止まり、光があっても光合成は頭打ちになります。強光に合わせて風通し(扇風機やサーキュレーター)を確保し、天葉の温度を上げ過ぎないようにします(Adams & Demmig-Adams, 1994)。用土の水切れが早くなるため、灌水頻度と量を見直し、乾き切る直前で次の水やりに入ると、根の酸欠を避けながら光を活かせます。
🥤肥料は、光量とセットで考えます。光が弱い環境で窒素を増やすと、柔らかい組織が伸びて徒長の温床になりがちです。逆に強光下では、窒素・カリ・微量要素が不足すると葉の展開が鈍り、光を受けても形が締まりません。光が強ければ栄養もやや積極的に、光が弱ければ控えめにという同期が基本です(Poorter et al., 2012)。強光・高温・乾燥が重なる夏は、土壌中の塩類濃度が上がりやすいため、定期的な洗い流し潅水で蓄積を防ぎます。
9. 季節運用の実践(慣光・遮光・冬の補光)
季節感知と冬の必要光量
🍂塊根植物や多肉植物は、日長(昼の長さ)や温度の変化を通して季節を感じ取る能力を持っています。アガベやパキポディウムの多くは、気温の低下や日照時間の短縮によって成長を抑え、半休眠のような状態に入ります。つまり、屋外で夏を過ごし、冬に室内へ取り込まれる場合でも、温度や日長の違いを手がかりに「季節の移り変わり」をある程度認識できるのです(Taiz & Zeiger, 2015)。
☀️では、冬の必要光量は夏と比べてどの程度変わるのでしょうか。夏の成長期には多くの種でDLI 20〜30 mol/m²/日が理想とされますが(Poorter et al., 2012)、冬は低温や短日で代謝そのものが鈍るため、必要なDLIはおおよそ半分程度に落ちます。実務的には10〜15 mol/m²/日を確保できれば休眠期の形を維持するには十分で、徒長の防止にも役立ちます。逆に「成長期と同じ強光」を無理に当てても、気温が伴わなければ光合成は進まず、葉焼けやストレスの原因になってしまいます。
❄️したがって、冬は「夏より必要光量が少なくてもよいが、ゼロにはできない」と理解するのが現実的です。最低限の光(10 mol前後)を補い、株を締めたまま春を迎えられるようにすることが徒長防止の鍵になります。
春の慣光と屋外への移行
🔁冬から春への切り替えは、株の健康と見た目を左右します。冬は室内の弱光で越した株を、春にいきなり直射に出すと葉焼けします。1〜2週間かけて段階的に慣光することが必要です。最初の数日は屋外の明るい日陰から始め、次に午前中の短い直射を加え、最後に日中の直射へと広げていきます。こうすることで葉の細胞が厚壁化し、強い光にも耐えられるようになります。
夏の強光と遮光管理
☀️夏は高温と強光が重なるため、葉焼けのリスクが最も高い季節です。真夏の正午前後は50%程度の遮光を用いて葉温の上昇を防ぐのが有効です。遮光ネットは黒よりも白やシルバーの拡散タイプが望ましく、直射をやわらげつつDLIを確保できます。加えて、サーキュレーターや自然風を活用し、蒸散による葉面冷却を助けます。
秋の光を使い切る工夫
🍁秋は日射角が下がり、気温が落ち着くことで安全にDLIを稼げる季節です。この時期に十分に光を当てると、塊根やロゼットが一段と締まります。秋は気温も比較的穏やかで、真夏ほど遮光を必要としないため、できるだけ直射に当て、植物体内に栄養と水分を蓄えさせることが翌年の生育にもつながります。
関連リンク:秋の光で太らせる:日照の使い切り
冬の補光と休眠維持
❄️冬は光も温度も不足しがちなため、株の姿を保つには工夫が必要です。最低限のDLI(10 mol程度)を目標に、LED照明を用いて補光するのが効果的です。点灯時間は12〜14時間を目安にし、室内でのDLI不足を補います。ただし、室温が低いまま強光を与えると葉焼けやストレスの原因になるため、光と温度のバランスを意識することが重要です。冬はあくまで「維持の季節」であり、成長を促す季節ではないことを念頭に置きましょう。
生育のモニタリングと調整
🔍季節ごとの管理では、常に株の反応を観察することが欠かせません。新葉の厚み、色、節間の長さ、葉の角度は光環境に敏感に反応します。徒長し始めると、新葉が薄く、節間が伸び、葉が上を向きます。逆に光が強すぎると、葉先の褐変や白化、表面のざらつきが出ます。これらの兆候は3〜7日程度で現れるため、遮光ネットの開閉、LEDの距離や点灯時間の調整を週単位で繰り返し、常に最適な光環境を維持します。
10. 強い光に耐える根づくりと用土(PHI BLENDという選択)
🧱強い光でDLIを引き上げると、蒸散が活発になり、鉢内はよく乾くが酸欠も起きやすい環境になります。徒長を抑えつつ健全に大きくするには、通気性が高く、速く乾いて、なおかつ適度に水分と養分を持てる用土が不可欠です。無機の骨格材は構造を支え、根に酸素を供給し、有機の繊維材は水分・養分の保持と根の微生物環境の安定に寄与します(Taiz & Zeiger, 2015)。
🔗当社のPHI BLENDは、無機質75%・有機質25%という「強い光に耐える比率」を基礎に、日向土・パーライト・ゼオライトで排水と通気を確保し、ココチップ・ココピートで必要最小限の保水・保肥をもたせています。強光・高温期の根腐れリスクを抑えつつ、DLIを引き上げた運用に追随しやすい設計です。詳しくは製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品ページ
参考文献
Adams, W. W., & Demmig-Adams, B. (1994). Photoinhibition and photoprotection in nature. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 45, 1–25. DOI: 10.1146/annurev.pp.45.060194.000245
Casal, J. J. (2013). Photoreceptor signaling networks in plant responses to shade. Annual Review of Plant Biology, 64, 403–427. DOI: 10.1146/annurev-arplant-050312-120221
Franklin, K. A., & Quail, P. H. (2010). Phytochrome functions in Arabidopsis development. Journal of Experimental Botany, 61(1), 11–24. DOI: 10.1093/jxb/erp304
Hemming, S., Dueck, T., Janse, J., & van Noort, F. (2008). The effect of diffuse light on crops. Acta Horticulturae, 801, 1293–1300. DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.801.158
Jenkins, G. I. (2017). Photomorphogenic responses to ultraviolet-B light. Current Opinion in Plant Biology, 37, 123–129. DOI: 10.1016/j.pbi.2017.04.003
Kaiser, E., Ouzounis, T., Giday, H., Schipper, R., Heuvelink, E., & Marcelis, L. F. M. (2019). Adding blue to red supplemental light increases biomass and yield of greenhouse-grown tomatoes, but only to an optimum. Frontiers in Plant Science, 10, 2002. DOI: 10.3389/fpls.2019.02002
Kong, Y., & Zheng, Y. (2024). Blue light as a versatile mediator of plant elongation: context matters. Plants, 13(1), 115. DOI: 10.3390/plants13010115
Levinson, R., Akbari, H., Berdahl, P., & Miller, W. (2010). Light transmission through glass: spectral transmittance of clear and coated glazing materials. Energy and Buildings, 42(2), 248–256. DOI: 10.1016/j.enbuild.2009.08.012
Li, T., Heuvelink, E., van Noort, F., & Marcelis, L. F. M. (2014). The advantage of diffuse light for horticultural production. Acta Horticulturae, 1037, 595–602. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1037.79
Nelson, J., & Bugbee, B. (2014). Economic analysis of greenhouse lighting: light emitting diodes vs. high intensity discharge fixtures. PLOS ONE, 9(6), e99010. DOI: 10.1371/journal.pone.0099010
Poorter, H., Niinemets, Ü., Ntagkas, N., et al. (2012). A meta-analysis of plant responses to light intensity for leaf mass, thickness, and photosynthetic capacity. New Phytologist, 193(4), 912–934. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2011.04029.x
Runkle, E. S., & Both, A. J. (2017). Greenhouse production research: Daily light integral—A useful tool for managing light in greenhouses. Michigan State University Extension. URL: https://www.canr.msu.edu/floriculture/uploads/files/DLI.pdf
Taiz, L., & Zeiger, E. (2015). Plant Physiology and Development (6th ed.). Sinauer Associates. (基礎生理の参照)
Zhen, S., & Bugbee, B. (2020). Far-red photons have equivalent efficiency to photons in the 400–700 nm waveband for photosynthesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 117(41), 23155–23162. DOI: 10.1073/pnas.2008966117
Apogee Instruments (2021). Converting illuminance (lux) to PPFD (µmol m⁻² s⁻¹): why it is complicated. Application Note. URL: https://www.apogeeinstruments.com/converting-lux-to-ppfd/
📝本稿は、塊根植物・多肉植物を美しく健康に育てることを目的に、光の「強さ」と「合計」、そして「質」を家庭で調整するための道筋をまとめました。まずは現在の光環境を測って見える化し、株の反応を観察しながら、距離・時間・光質を少しずつ整えてください。強い光を活かせる根と用土を用意すれば、徒長は止まり、株は締まっていきます。