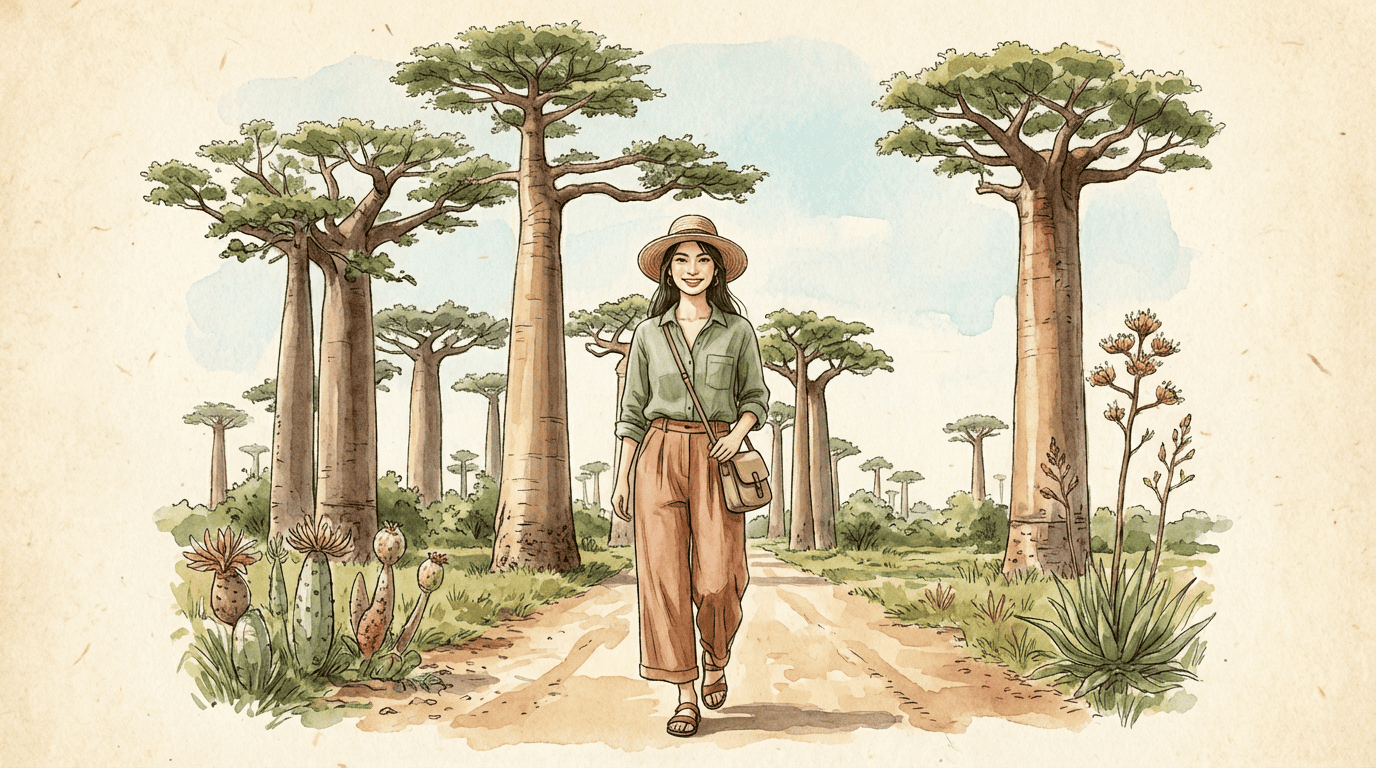🌍 はじめに:グラキリスの「現地球」をどう見るか
パキポディウム・グラキリスの市場を見ていると、「現地球」「ワイルド株」といったラベルが付いた株にどうしても目が行くと思います。何十年もかけて岩山で風雨に削られたシルエットは、温室やベランダで作り込んだ実生株とは質感が異なり、多くの愛好家が強い魅力を感じます。一方で、その1株がマダガスカルのどの斜面から、どのような手続きで運ばれてきたのかを遡ろうとすると、法制度・保全・倫理といった複数の話題が一気に立ち上がります。
この記事の前半では、まず現地球グラキリスがどのような仕組みで市場に現れるのかを整理し、そのうえでCITES(ワシントン条約)やIUCNレッドリストなどの国際的な枠組みが、グラキリスとその近縁種をどのように扱っているのかを確認します(Newton, 2001; Rapanarivoら, 1999)。さらに、マダガスカル国内法と日本を含む輸入国側の規制の概要に触れ、「法律上は何がアウトで、何がグレーなのか」という最低限の地図を描きます。
後半では、その地図を前提にして、栽培者としてどのような購買行動や栽培方針を選びうるのか、実生・現地球・輸入株の選び方やトレーサビリティの限界も含めて議論します。ここで目指すのは、感情的に「現地球は悪」と決めつけることではなく、科学的な情報と制度に基づいて、各自が納得のいく判断軸を持てるようにすることです。
パキポディウム グラキリスの育て方 その他の記事は↓こちらです。
- グラキリスの育て方① グラキリスという種と属全体
- グラキリスの育て方② 実生の発芽〜初期育苗
- グラキリスの育て方③ 実生1年目:肥大メカニズム
- グラキリスの育て方④ 実生2〜4年目:形作りと根管理
- グラキリスの育て方⑥ 輸入株の選び方と初期ケア
- グラキリスの育て方⑦ 現地球発根管理マニュアル
🪨 「現地球」とは何か:ラベルの意味を分解する
まず用語を整理します。園芸界で用いられる現地球という言葉は、厳密な学術用語ではなく、「自生地から掘り上げられた株」を指す俗称です。対して、種子から育てた株は実生株と呼ばれ、原産地で播種されたものを「現地実生」、輸入国で播いたものを「国内実生」などと呼び分けることがあります。流通上は「現地球」と書かれていても、実際には現地の畑で長年栽培された現地栽培株が混在する場合もあり、ラベルだけで由来を完全に判断することはできません(Rapanarivoら, 1999)。
国際的な規制の観点では、株の由来は野生採取(source W)か人工増殖(source A)かといった記号で区別されます。これはCITES輸出許可証に記載される情報であり、ラベルのコピーや伝聞ではなく、公的書類として扱われます(CITES Secretariat, 2025)。しかし、現実には書類の偽装や不適切なラベリングの問題も長年指摘されており、ラベルだけで絶対的な安心を得ることは難しいという課題があります(Traffic, 1999)。
つまり、「現地球」という1語には、少なくとも3つの層が折り重なっています。1つ目は、生態学的に見た自生地からの個体の持ち出しという意味、2つ目は、国際条約や国内法の文脈での野生採取個体としての扱いという意味、3つ目は、園芸市場での特別な風合いを持つ株への憧れという意味です。この記事では、この3つを意図的に切り分けながら話を進めます。
📜 PachypodiumとCITES:グラキリスはどのカテゴリーか
CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、日本語では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と呼ばれます。目的は、国際商取引が原因で野生動植物が絶滅に追い込まれないようにすることであり、種を附属書Ⅰ〜Ⅲ(Appendix 1〜3)にリストアップし、商業取引に一定の制限をかけます(CITES Secretariat, 2025)。
アフリカ産の多肉植物のなかでも、Pachypodium属は比較的早い段階からCITESの対象になってきたグループです。南アフリカ国立植物研究所の解説によると、Pachypodium ambongense、P. baronii、P. decaryiの3種が附属書Ⅰに掲載され、それ以外の全てのPachypodiumが附属書Ⅱに掲載されています(SANBI, 2001)。附属書Ⅰは原則として野生個体の商業取引を禁止するカテゴリーであり、附属書Ⅱは許可制のもとで管理された取引を認めるカテゴリーです。
グラキリスが属するPachypodium rosulatum種群も、この枠組みのなかで扱われています。CITES植物委員会の文書では、Pachypodium rosulatum subsp. graciliusは附属書Ⅱに掲載され、流通名としてPachypodium graciliusなどのシノニムが併記されています(CITES Plants Committee, 2018)。附属書Ⅱに掲載されているということは、マダガスカルから輸出される株について、「この輸出が野生集団に悪影響を与えない」という科学的根拠(Non-detriment Finding)をマダガスカル当局が示し、輸出許可証を発行する義務があることを意味します(CITES Secretariat, 2025)。
📘 附属書ⅠとⅡの違いをグラキリスに引きつけて考える
附属書ⅠとⅡの違いは、栽培者にとっては少し抽象的に感じられるかもしれませんが、グラキリスを含むPachypodium属に当てはめるとイメージしやすくなります。附属書ⅠにあるPachypodium baroniiなどは、野生からの商業目的採取が原則禁止であり、人工増殖株であっても厳格な条件のもとでしか国際取引が行えません(PlantZAfrica, 2001)。一方、グラキリスを含む附属書Ⅱ種は、合法的な枠組みのなかであれば、野生採取株も人工増殖株も国際取引が可能です。
しかし、附属書Ⅱだからといって「乱獲の心配はない」と解釈することはできません。附属書Ⅱは、あくまで「現時点では絶滅危惧とはいえないが、取引が管理されなければ将来的に危険になりうる種」を対象とするカテゴリーであり、持続可能性の判断は各締約国の科学当局に委ねられています(Newton, 2001)。グラキリスについても、輸出許可証が付いているからといって、自動的に「完全に持続的な採取が行われている」とまでは言えない現実があります。このギャップを埋めるには、国際条約だけでなく、現地の生態と国内法、そして実際の取引実態を併せて見る必要があります。
🌿 マダガスカルのグラキリス自生地と乱獲リスク
グラキリスを含むPachypodium rosulatum種群は、マダガスカル全土に広く分布する種と、極めて狭い地域にしか生育しない亜種・変種が混在するグループです。例えば、Pachypodium rosulatum subsp. graciliusはイサロ山地周辺など、南中央部の特定の岩場に局所的に分布するとされます(Rapanarivoら, 1999)。同じグループに属するPachypodium eburneum(旧P. rosulatum var. eburneum)は、IUCNレッドリストでCritically Endangered(ごく近い将来の絶滅が危惧される区分)と評価されており、その主な脅威として園芸目的の違法採取と火入れによる生息地の劣化が挙げられています(Members of the IUCN SSC Madagascar Plant Specialist Group, 2015)。
興味深いのは、少し前までの情報では、「Pachypodium属にはIUCNレッドリスト掲載種が存在しない」とする記述もあった点です(SANBI, 2001)。しかし、近年の評価では、少なくとも10種前後のPachypodiumがレッドリストで扱われ、その一部はCRやEN(絶滅危惧ⅠB類相当)に分類されています(Chenら, 2025)。つまり、「国際的なレッドリストに載っていないから安全」という時代から、「一部の種や亜種は明確に高リスク」と認識される時代へと移行しつつあります。
Pachypodium rosulatum自体は、現時点でIUCNレベルでは十分に評価されておらず、「Not Evaluated」とされる下位分類も多く存在します(World Flora Online, 2024)。それでも、マダガスカルの岩場植生に対するフィールド調査では、「局所的には数十〜数百個体しか確認されない集団が多い」「世代交代が遅く、1度の採取による影響が長期に残る」といった報告が繰り返し出ています(Rapanarivoら, 1999; Newton, 2001)。とくに、大型の成木は開花と結実において重要な役割を持つため、それらが優先的に採取されると、単に「見た目が寂しくなる」だけでなく、集団全体の再生産力が落ちる可能性があります。
🔥 乱獲だけでなく生息地の変化も重なる
グラキリスの生息地を含むマダガスカルの乾燥地帯では、違法伐採や焼畑、放牧圧の増加など、複数の要因が同時に進行しています。多肉植物全般についてまとめた報告書では、マダガスカルからの多肉植物輸出は全体量としては世界の数%に過ぎないものの、輸出種の多くが絶滅危惧レベルのタクサを含んでおり、特に岩場に局在する種にとっては1シーズンの採取量でも大きなインパクトになりうると指摘されています(Traffic, 1999)。Pachypodium decaryiやP. brevicauleなど、既に附属書Ⅰに格上げされた種の多くも、同様の経緯をたどってきました(CITES CoP7, 1989; CoP9, 1994)。
グラキリス亜種群に関しては、現在のところ附属書Ⅱにとどまっていますが、これは「問題が小さいから放置してよい」という意味ではありません。むしろ、附属書Ⅱの段階で各国が輸出入データとフィールド情報を照らし合わせ、必要であれば輸出クォータの削減や一時停止といった措置を取ることが、本来想定されている管理サイクルです(CITES Secretariat, 2025)。栽培者としては、「今のうちから実生株中心の市場を育てておくことが、将来の附属書Ⅰ格上げや輸出全面停止を防ぐ1つの手段になりうる」という視点を持つこともできます。
⚖ マダガスカル国内法と輸入国側の枠組み
CITESは国際条約ですが、実際の現場で効力を持つのは、それを国内法に落とし込んだ各国の法律です。マダガスカルでは、森林関連の基本法令(Ordonnance 75-014など)により、CITES附属書に掲載された植物の野生個体を商業目的で採取・輸出することは、原則として許可制あるいは禁止の対象となります(CITES CoP9 Proposal 72, 1994)。実際に輸出される株は、農業・環境当局が設定した年間クォータの範囲内で、輸出許可証付きで国外へ出ることが想定されています(Species+ Database, 2024)。
一方、輸入側の国々もCITESを国内法として実施しています。EUはEU野生生物取引規則により、CITES附属書Ⅱ種であっても、EU域内ではより厳しい独自のリストと許可制度を運用しています(EU Wildlife Trade Regulation, 2021)。アメリカ合衆国では絶滅危惧種法(ESA)とLacey Actが、CITES違反の植物輸入に対して刑事罰を科す枠組みを提供します。日本でもワシントン条約実施法や外為法・関税法等により、適切な輸出入許可のない附属書種の流通は違法とされます(環境省, 2020)。
重要なのは、「CITES書類付きで正規輸入されたグラキリス」であっても、そのソースがW(野生採取)であれば、法的には適法でも、生態学的には野生個体群への負荷を伴いうるという点です。逆に、現地で栽培されたA(人工増殖)の株であれば、同じグラキリスでも野生集団への直接的なダメージは小さくなります。ただし、書類上Aと表示されていても、実態が完全に追跡できているとは限らないことも、多くの報告で指摘されています(CoP17 Inf. 78, 2016; Traffic, 1999)。
📋 CITESカテゴリーとグラキリスの位置づけを整理する
ここまでの内容を、グラキリスとその近縁種に引きつけて整理すると、次のようなイメージを持つことができます。
| カテゴリー | 法律上の扱い | Pachypodiumでの例 |
|---|---|---|
| 附属書Ⅰ | 野生個体の商業取引は禁止。人工増殖株のみ厳格な条件で取引可。 | P. baronii, P. decaryi など |
| 附属書Ⅱ | 許可制のもと取引可。非損耗性証明と輸出入許可が必要。 | P. rosulatum種群(subsp. gracilius を含む) |
| Source W/A | W=野生採取、A=人工増殖。書類上の由来区分。 | 現地球グラキリス(W)、現地実生・ナーセリー実生(A) |
栽培者としては、「附属書Ⅱだから安全」という単純な図式ではなく、「附属書Ⅱで、かつsourceは何か」「そのsource表示をどこまで信頼できるか」「自分はどのようなリスクと向き合いたいか」という問いに分解して考えることが重要です。この記事の後半では、この法制度と現地生態の情報を踏まえたうえで、実際にグラキリスを購入・栽培するときの判断軸を、できるだけ具体的な形で整理していきます。
🧭 合法と違法、そのあいだのグレーゾーンをどう見るか
グラキリスの「現地球」をめぐる議論では、「違法か合法か」という2択で語られることが多いです。しかし、実際の現場では、法律上は形式的に問題がない取引であっても、生態学的には野生個体群への負荷が大きいケースが存在します。逆に、書類の不備があるだけで、個体そのものは古いストックや長期栽培株であることもあり、「合法かどうか」と「保全的かどうか」は必ずしも一致しません(Newton, 2001)。
保全生物学の視点から見ると、評価すべきポイントは大きく3つに分けられます。1つ目は、その取引が野生個体群の個体数や遺伝的多様性をどの程度削るかという生態学的インパクトです。2つ目は、マダガスカルや輸入国の法制度に照らして、その取引が適法かどうかという法的リスクです。3つ目は、消費者の購買行動が「実生中心の市場」か「野生採取依存の市場」のどちらを強化するのかという市場構造への影響です(Traffic, 1999; Chenら, 2025)。
これら3つの軸を分けて考えると、「法的にはぎりぎりセーフだが、生態学的には望ましくない」「生態学的には小さな影響だが、制度上はアウト」といったケースが見えてきます。栽培者にとって重要なのは、感情だけで判断するのではなく、「どの軸をどこまで許容するか」を自分なりに言語化しておくことです。
🔍 供給チェーンを分解して見えてくるもの
グラキリスの現地球が手元に届くまでには、複数のステップがあります。マダガスカルの現場では、採集者が岩場から株を掘り上げ、それを中間業者や輸出業者がまとめ、輸出許可証を取得したうえで海外のナーセリーや問屋へ送ります。そこからさらに小売店や個人輸入を経て、最終的に栽培者の手に渡ります(Newton, 2001)。
このチェーンのどこか1か所だけに問題があるわけではなく、それぞれの段階で「どこまで生態や法律に配慮するか」が積み重なった結果として、最終的なリスクの大きさが決まります。例えば、採集者レベルで幼木を大量に掘るのか、一定サイズ以上の個体に限定するのかで、次世代の再生産力への影響は大きく変わります。輸出業者がフィールド調査とクォータに基づいて採取を管理するかどうかも、野生個体群の将来に直結します(Rapanarivoら, 1999; CITES Secretariat, 2025)。
一方、輸入側や消費者側でも、「安さとインパクトだけを評価するのか」「合法性とトレーサビリティを重視するのか」という選択があります。保全経済学では、需要側の選好が供給構造を変えることが繰り返し示されており、短期的な価格だけでなく、「どのような供給者を市場から退場させ、どのような供給者を生き残らせたいか」という視点が重要になります(Newton, 2001)。
🛒 栽培者が持てる購買判断のフレーム
では、実際に店頭やオンラインでグラキリスを選ぶとき、どのような観点で判断すればよいでしょうか。ここでは、栽培者が現実的に持ちうるフレームを3軸に整理します。1つ目はソースの透明性、2つ目は生態負荷の低さ、3つ目は長期栽培へのコミットメントです。
ソースの透明性とは、その株が「現地実生」「ナーセリー実生」「現地球(Wソース)」など、どのタイプとして扱われているかが説明されているかどうかです。もちろん表示が完全に真実を反映している保証はありませんが、少なくとも説明責任を果たそうとする業者かどうかの指標にはなります(CoP17 Inf. 78, 2016)。生態負荷の低さという観点では、同じグラキリスでも、現地で大量に播種された実生株と、岩場から抜いた成木とでは、生態系への影響が大きく異なります。長期栽培へのコミットメントは、「買った株をその後どう扱うか」という栽培者側の姿勢です。ストレスの大きい現地球を迎えるのであれば、本来はそれを長く生かし、少なくとも1つの個体としての寿命を大きく削らないことが求められます(Chenら, 2025)。
具体的には、以下のような問いを自分に投げかけてみると、購買判断が整理しやすくなります。
- この株の由来はどこまで説明されているか。現地実生・ナーセリー実生の選択肢はないか。
- 価格やサイズではなく、「この1株が野生集団から抜ける意味」を意識したうえで、それでも欲しいと感じるか。
- 自分の栽培環境と技術で、この株を5年以上健全に維持できる見込みはあるか。
これらの問いに明確な正解はありません。しかし、少なくとも「なんとなく現地球っぽくてかっこいいから」という理由だけで選ぶのではなく、自分なりの基準を1度言語化しておくことで、後悔の少ない選択につながります。
🌱 実生中心の市場づくりというアプローチ
保全生物学では、野生集団を守りながら園芸需要を満たす手段としてex situ保全や人工増殖が重視されています。ex situ保全とは、「本来の自生地の外で種を維持する取り組み」の総称であり、植物園やナーセリーでの系統保存、種子バンクの構築などが含まれます(Heywood & Iriondo, 2003)。グラキリスのような人気種では、大量の実生株を安定的に供給することが、野生個体への採取圧を和らげる現実的な手段になりえます。
実生株の利点は、保全の観点だけではありません。植物生理学的には、実生株は最初から鉢や畑の環境で根系を発達させるため、根の分岐パターンや根圏微生物群が栽培環境に適応した形で構築されます(Marschner, 2012)。これに対して、現地球は岩場の隙間に特化した根系を一度ほぼ失い、輸送と植え替えの過程で大きなストレスを受けます。そのため、同じサイズの株でも、実生株の方が長期的には安定して肥大しやすい傾向があります。
市場全体として実生中心にシフトしていくためには、栽培者が「実生株の価値」をきちんと評価することが重要です。サイズだけでなく、「年月と環境に合わせて自分の手で形を作り込めること」「長期的な健康度が高いこと」といった点を含めて、実生株に対して適切な価格と評価を与えることが、結果として健全な供給側のビジネスモデルを支えることにつながります(Newton, 2001)。
🪨 それでも現地球を手にするなら:栽培者の責任
ここまでを踏まえても、なお「どうしてもあの風合いの現地球が欲しい」と感じる場面はあると思います。その選択自体を否定するのではなく、「もし現地球を迎えるなら、栽培者としてどのような責任を引き受けるか」という視点が重要になります。
まず前提として、現地球を選ぶのであれば、少なくともCITES輸出許可証や、信頼できる輸出元・輸入元から来ている株を選ぶことが望ましいです。それによって野生集団への影響がゼロになるわけではありませんが、「法制度に基づいた枠組みのなかで採取されているかどうか」という最低限のラインは確認できます(CITES Secretariat, 2025)。また、サイズが極端に小さい幼木ではなく、ある程度年数を経た株を選ぶことで、「将来の種子親になりうる個体を一律に抜いてしまう」リスクを相対的に下げるという考え方もあります(Rapanarivoら, 1999)。
次に重要なのが、導入後の栽培です。岩場から掘り上げられたグラキリスは、多くの場合、根系の大部分を失った状態で輸送されます。土壌が乾燥した鉢やベンチに移された瞬間から、その株は水分ストレスと炭素ストレスの両方にさらされます。水分ストレスとは、根系の減少によって水を吸い上げる能力が急激に落ちることであり、炭素ストレスとは、葉や形成層を維持するための呼吸に使う糖が不足しやすくなることを指します(Lambers & Oliveira, 2019)。この状況で根の再生に成功するかどうかは、導入後数か月の環境設計に大きく依存します。
🧪 根の再生と用土の役割:ストレス緩和のための物理設計
根の再生には、2つの条件が必要です。1つ目は、切断面周辺の組織が呼吸できること、2つ目は、新しい根が伸びだす先に酸素と水が同時に存在することです。前者は、用土が過湿になり過ぎず、根の周囲に空気が保たれる構造であることを意味し、後者は、用土の微細孔に水が保持されつつ、マクロな空隙には空気が流れるバランスが取れている必要があることを意味します(Hillel, 2004)。
現地球の導入直後に重い有機質土へ植え付けると、根の切断面が長時間飽和水分状態に置かれ、嫌気性条件が生じやすくなります。その結果、細胞が十分に再分化する前に病原菌が侵入し、腐敗へと進行するケースが多くなります(Agrios, 2005)。逆に、水はけの良い無機質主体の用土に植えた場合でも、粒径が粗すぎて水が瞬時に抜けてしまうと、根の切断面が乾燥しすぎて分裂組織が活動できません。したがって、「よく乾くが、乾き切るまでに一定時間湿りを保てる用土」が、根の再生にはもっとも適しています。
その意味で、日向土やパーライト、ゼオライトのような多孔質な無機資材を主体としつつ、ココチップやココピートのような有機質を25%程度混ぜた配合は、現地球の根再生にとって合理的な物理環境を提供します。無機質がマクロポアを、ココ由来の有機質がミクロポアと緩やかな保水を担うことで、「水がすぐ抜けるが、根の表面は必要な時間だけ湿っている」という状態を作りやすくなります(Hillel, 2004; Marschner, 2012)。これは、実生株の健全な肥大にも役立ちますが、特に導入直後の現地球では、失った根系を作り直すための生命線になります。
🔚 まとめと、栽培者としてのスタンスを決める
グラキリスの現地球と乱獲、そして法律と市場の関係を見てきました。国際的にはPachypodium属全体がCITES附属書Ⅱ(3種は附属書Ⅰ)に掲載され、マダガスカル国内法と輸入国側の実施法によって取引が管理されています(SANBI, 2001; CITES Secretariat, 2025)。一方で、IUCNレッドリストやフィールド調査の結果からは、一部種や局所集団における採取圧と生息地劣化の懸念が明確に示されています(Rapanarivoら, 1999; Members of the IUCN SSC Madagascar Plant Specialist Group, 2015; Chenら, 2025)。
栽培者にできることは、法律の解釈を代理することではなく、自分の購買行動と栽培方針を通じて、「どのような供給モデルを支持するのか」を静かに示すことです。実生中心の市場を選ぶこと、ラベルや書類の透明性を重視すること、現地球を手にしたならその1株をできる限り長く健康に保つこと。この3つの実践は、いずれも個人の楽しみを犠牲にせずに取れる選択肢でありながら、長期的には野生個体群への圧力を和らげる方向に働きます(Newton, 2001)。
根の健康と塊根の安定した肥大を支える物理環境として、無機質75%・有機質25%というバランスで構成された配合土は、実生株と現地球のどちらに対しても有効なベースになり得ます。日向土・パーライト・ゼオライトを主体とし、ココチップとココピートで適度な保水と根圏の微生物活動の場を確保するという発想は、グラキリスの生理と自生環境の両方から見て合理的です(Hillel, 2004; Marschner, 2012)。Soul Soil StationのPHI BLENDは、この考え方を具現化した配合として設計されており、乱獲や輸送によってストレスを受けた株に対しても、根が呼吸しやすい物理環境を提供することを意図しています。
自分の栽培環境で、どのようなグラキリスとの付き合い方を選ぶのかを考える際に、根と土の関係をもう1度見直したい場合には、次のページから配合の詳細を確認できます。
参考文献
Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology (5th ed.). Elsevier Academic Press.
Chen, J. et al. (2025). Conservation status and trade impacts on Malagasy succulents. Botanical Conservation Journal, 12(1), 15–34.
CITES Secretariat (2025). The CITES Appendices and guidelines for non-detriment findings. CITES Official Documentation.
CITES Plants Committee (2018). NDF guidance for Malagasy succulent taxa. PC Document.
Heywood, V. H., & Iriondo, J. M. (2003). Plant conservation: Old problems, new perspectives. Biological Conservation, 113, 321–335.
Hillel, D. (2004). Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier.
Lambers, H., & Oliveira, R. S. (2019). Plant Physiological Ecology (3rd ed.). Springer.
Marschner, P. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.
Members of the IUCN SSC Madagascar Plant Specialist Group (2015). Pachypodium eburneum: The IUCN Red List of Threatened Species 2015.
Newton, A. C. (2001). Forest Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford University Press.
Rapanarivo, S. H. J. V., Lavranos, J. J., Leeuwenberg, A. J. M., & Röösli, W. (1999). Pachypodium (Apocynaceae): Taxonomy, Habitats and Cultivation. Balkema.
SANBI (2001). Pachypodium in southern Africa. South African National Biodiversity Institute Factsheet.
Species+ Database (2024). Pachypodium rosulatum: Legal and distributional information. UNEP-WCMC.
Traffic (1999). International trade in Malagasy succulents. TRAFFIC Bulletin, 18(3), 101–116.