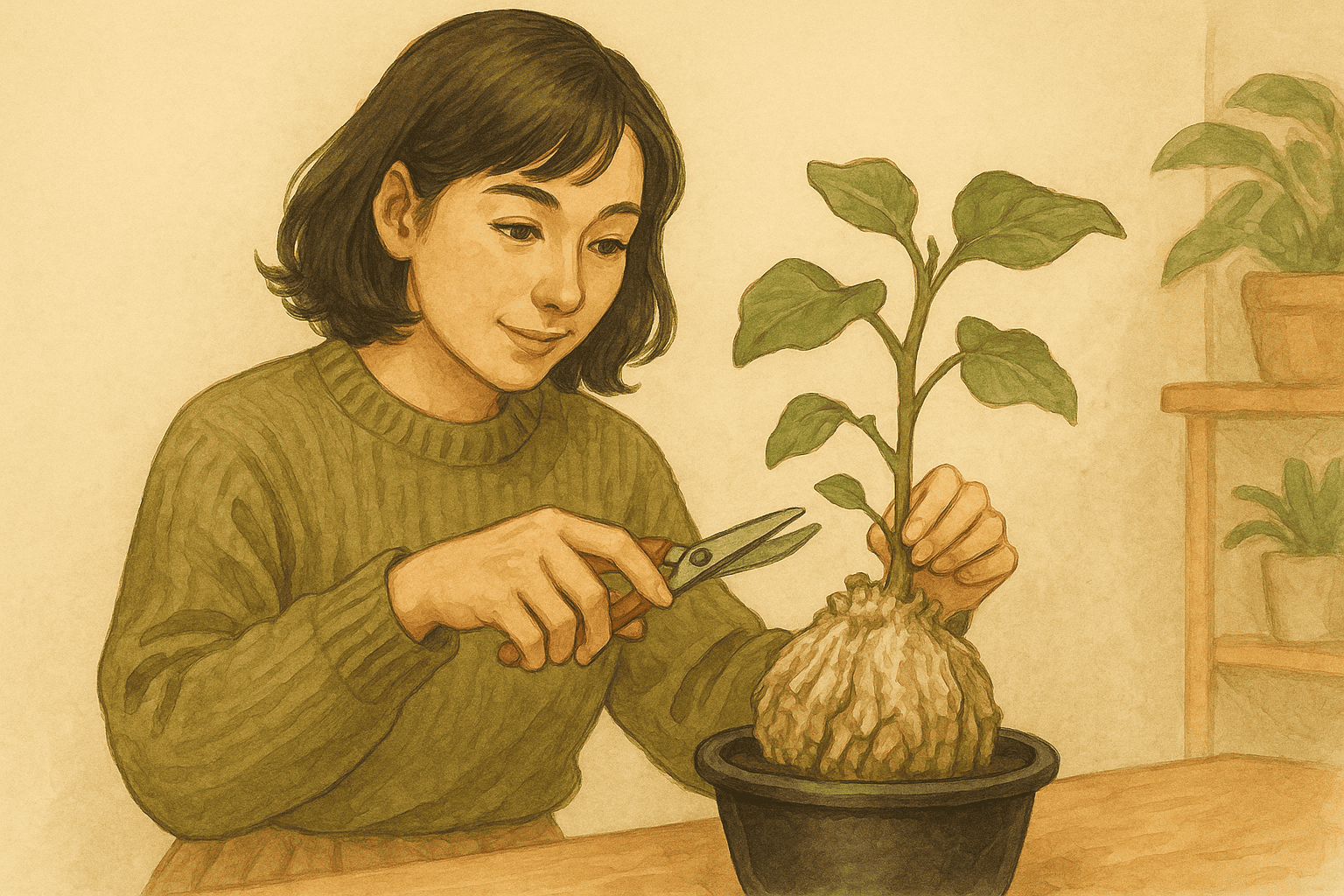✂️剪定と成長の関係性:刺激で「根づく力」を設計する
剪定や断根は見た目を整えるだけではありません。傷や曲げといった刺激に反応して、植物の内部ではホルモンの分布と養分の流れが組み替わり、切り口周辺でカルス(修復のためにできる未分化組織)や不定根(茎・葉など本来の根以外から出る根)が生まれます(Hartmann & Kester, 2011; Taiz & Zeiger, 2015)。この記事では、日本での栽培(冬は室内、それ以外は室内または屋外)を前提に、アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアを例に、実務に落とし込める数値目安とともに解説します。
💡最初におさえる要点(モバイル向け簡潔版)
✂️ 剪定(枝・茎)をすると、先端の支配力が弱まり側芽が動きやすくなります。同時に、葉で作られた養分の送り先が変わり、これまで頂部に集中していた分が根や新しい芽へ再配分されます。強すぎる刈り込みは光合成の落ち込みで回復が遅れるため、まずは軽〜中度が安全です(Cline, 1997; Kozlowski & Pallardy, 1997)。
🪓 断根(根剪定)は、切口の少し後ろから側根が複数出やすくなります。一度に切るのは根量の20〜40%を上限にして、切り口はよく乾かしてから植えると腐敗を避けやすいです(Kozlowski & Pallardy, 1997; Hartmann & Kester, 2011)。
🪢 屈折刺激(曲げ・誘引)は、枝角を変えることでホルモン分布が変わり、徒長を抑えつつ側芽が動きやすくなります。果樹の知見では枝角45〜60°が目安です(Wertheim, 1984)。
🧪 発根ホルモン(IBA/NAA)は切り口の脱分化と根原基の分化を後押しします。液剤のクイックディップはIBA 0.05〜0.8%相当が一般的な範囲です(Hartmann & Kester, 2011; Davies, 2010)。
📏 環境目安は、発根床温度22〜28℃、明るい日陰、通気・排水のよい用土、空中湿度60〜80%。用土は全孔隙率60〜80%の中で空気孔隙率15〜25%を確保できる粒度が安定します(Handreck & Black, 2010; Bunt, 1988; Hartmann & Kester, 2011)。
🌱1. なぜ剪定で根が動くのか:ホルモンと「流れ」の再設計
オーキシン(茎頂で合成され下へ流れる成長ホルモン)は根の形成と伸長を促し、サイトカイニン(根で合成され上へ動くホルモン)は芽の分化を促します。剪定で先端がなくなると頂芽優勢(頂部が側芽を抑える性質)が弱まり、側芽が伸びやすくなります(Cline, 1997)。このとき葉で作られた糖や栄養の送り先(シンク)も変わり、従来は頂部へ向かっていた流れが、根や残った芽へ振り向けられるようになります。言い換えると、剪定は「どこを優先的に育てるか」という資源の配分計画を作り替える操作です(Taiz & Zeiger, 2015; Druege et al., 2019)。
ただし、葉を落としすぎると炭素同化(=光合成によって二酸化炭素を有機物に変える作用)が不足し、新しい枝の形成や根の再生が遅れます。地上部と地下部のバランスを保つため、最初は軽〜中度の剪定にとどめ、株の反応を見ながら段階的に調整します(Kozlowski & Pallardy, 1997)。
🪓2. 断根の科学:どこまで切って、どう待つか
断根は太い根の先端優位を断ち、切口の後方で側根原基が活性化して、細い新根が複数立ち上がるきっかけになります。細根は吸水・養分吸収の主力なので、適度な断根は「同じ鉢容積でより効率のよい根系」を作り直す作業だと考えられます(Hartmann & Kester, 2011)。
安全域の目安は「一度に20〜40%まで」。これを超えると水分供給とホルモンの流れが急減し、回復が難しくなります。切断後はよく乾かす→浅く置く→少量の水から始めるの順で管理すると腐敗を避けやすくなります(Kozlowski & Pallardy, 1997; Hartmann & Kester, 2011)。移植や鉢替えの数週間〜数か月前に根切りを行い、切口縁に新根が縁取りした若い根鉢を作っておく手法も有効です(Hartmann & Kester, 2011)。
🪢3. 屈折刺激(曲げ・誘引):徒長を抑え、側芽を起こす
屈折刺激は、枝や茎に角度を付けることで内部のホルモン分布が変わり、徒長が抑えられて側芽が伸びやすくなります。果樹栽培では45〜60°の枝角が分枝・花芽誘導の目安とされ、観葉・多肉でも腋芽の動きがよくなります(Wertheim, 1984)。機械刺激は一時的にエチレン(ストレス応答ホルモン)を増やし、細胞の伸長を抑えつつ太さ方向の成長を促します。多肉は組織が脆いので、曲げはゆっくりと行い、必要なら柔らかい素材で固定して数週間かけて角度を作ります(Salisbury & Ross, 1992)。
🧬4. 傷から根ができる手順:カルス→根原基→不定根
切断直後、傷口ではまず酸化ストレスの制御と細胞壁の修復が進み、その後にカルスが安定化します。温度が合えば3〜14日でカルスが落ち着き、条件がそろうと2〜6週間で根原基が分化して不定根が伸び始めます(Hartmann & Kester, 2011)。このプロセスは糖の供給とオーキシンに強く依存し、低温・過湿・低酸素で大きく遅れます(Druege et al., 2019)。多肉・塊根では「切ってすぐ挿す」より、まずしっかり乾かすほうが安全に進みます。
🧪5. 発根ホルモンの使い方:濃度とフォーム
インドール酪酸(IBA)やナフチル酢酸(NAA)は、切断面の細胞を一度「赤ちゃん状態」に戻して(脱分化)、根になる方向へ導きます。液剤のクイックディップ(数秒浸漬)は、草本〜軟らかい多肉で0.05〜0.15%、半硬化〜木化で0.15〜0.8%がよく用いられます。粉剤は薄く均一が原則で、厚塗りはカルス過多や黒変の原因になります(Hartmann & Kester, 2011; Davies, 2010)。発根ステージでは、芽を増やすサイトカイニンは抑えめにし、オーキシン主導で進めると安定します(Cline, 1997)。
🏺6. 用土と環境設計:空気・水・温度・光のバランス
発根の土台は通気と排水です。容器栽培では全孔隙率60〜80%のうち、空気が占める割合である空気孔隙率を15〜25%確保すると、根が酸欠になりにくく安定します(Handreck & Black, 2010; Bunt, 1988)。発根床の温度は22〜28℃が目安で、光は明るい日陰が基本です。葉の同化を確保しつつ負荷を抑えるには、PPFD(葉が受ける光量の指標)で100〜300 μmol m−2 s−1程度が扱いやすい範囲です(Hartmann & Kester, 2011)。空中湿度は60〜80%に留め、毎日換気して嫌気化と病原の定着を防ぎます(Taiz & Zeiger, 2015)。
🦠7. 微生物と衛生:腐らせない段取り
切り口は病原の入口になりやすいため、刃物の消毒、乾燥期間、通風の確保が基本です。樹木分野で使われる傷口被覆剤は乾きの遅延や内部腐朽を助長する報告があり、多肉・塊根では原則として不要です(Chalker‑Scott, 2007)。一方、根圏の有益微生物(菌根菌やPGPR=植物成長促進細菌)は、リン吸収やオーキシン様物質の産生で発根を助ける可能性があります。まずは清潔で物理性の良い培地を基本にし、必要に応じて微生物資材を試すとよいです(Lugtenberg & Kamilova, 2009; Spaepen et al., 2007)。
🌵8. 代表属での実践:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア
アガベはロゼットで頂芽優勢が強く、頂部を切ると子株(吸芽)が動きやすくなります。頭部挿しはしっかり乾かしてから粗めの用土へ浅く設置し、温度22〜28℃で管理します。根の整理は枯根・腐根の除去を中心にし、太根は小刻みに分けて切ると安全です(Hartmann & Kester, 2011)。
パキポディウムは発根が遅い種が多く、剪定後の乾燥期間を長めにとります。強光は避け、温度を安定させ、最初の吸水は新根の白点が見えてからにすると腐敗リスクを減らせます(Druege et al., 2019)。
ユーフォルビアは乳液を流水でよく洗い流し、乾燥後に挿すと歩留まりが上がります。節ごとに休眠芽が多く、刈り込みで株姿を作りやすいです(Taiz & Zeiger, 2015)。
🗾9. 日本の季節に合わせる:時期と水やり
日本の平地基準では、夏型の多肉・塊根は春〜初夏に剪定・植え替えを行うと回復が速いです。剪定後は直射を避け、風を通し、発根までは無潅水〜霧吹き程度にとどめます。冬は室内で最低温度10〜12℃以上を確保し、原則剪定は避けます。どうしても冬に処置が必要なときは切除量を最小にし、完全乾燥気味で発根を待ちます(Hartmann & Kester, 2011; Taiz & Zeiger, 2015)。
🧭10. つまずきやすいポイントと立て直し
腐敗の多くは過湿・低温・無風の重なりです。失敗しやすいのは「切ってすぐに深植えしてたっぷり潅水」のパターンです。乾かす→浅く置く→底面から少量の順で進めると安全に立ち上がります。動きが鈍いときは温度を24〜26℃へ上げ、夜間だけ軽く加湿してカルスの代謝を促します。断根で萎れるときは葉面積を一時的に減らすか、光量を少し落として蒸散負荷を下げます(Kozlowski & Pallardy, 1997; Druege et al., 2019)。
🔧付記:基質設計とPHI BLENDの位置づけ
発根期は「通気と排水が高く、必要最小限の保水がある」配合が有利です(Handreck & Black, 2010; Bunt, 1988)。この考え方に沿う配合として、PHI BLENDは無機質75%(日向土・パーライト・ゼオライト)と有機質25%(ココチップ・ココピート)で構成され、粗〜中粒中心の空隙構造がカルス期の嫌気化を避けながら新根の侵入を助けます。詳細は製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品情報へ
発根・発芽関連の総合記事はこちら:塊根・多肉植物の発根・発芽完全ガイド【決定版】
📚参考文献
Aloni, R., Aloni, E., Langhans, M., & Ullrich, C. I. (2006). Role of auxin and cytokinin in vascular differentiation. Planta.
Bunt, A. C. (1988). Media and Mixes for Container-Grown Plants. Unwin Hyman.
Chalker‑Scott, L. (2007). The Myth of Wound Dressings. Washington State University Extension.
Cline, M. G. (1997). Concepts and terminology of apical dominance. American Journal of Botany.
Davies, P. J. (Ed.). (2010). Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action! Springer.
Druege, U., Hilo, A., Pérez‑Pérez, J. M., et al. (2019). Adventitious root formation: carbohydrate and hormonal control. Frontiers in Plant Science.
Handreck, K., & Black, N. (2010). Growing Media for Ornamental Plants and Turf (5th ed.). UNSW Press.
Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies Jr., F. T., & Geneve, R. L. (2011). Plant Propagation: Principles and Practices (8th/9th ed.). Prentice Hall.
Kozlowski, T. T., & Pallardy, S. G. (1997). Physiology of Woody Plants. Academic Press.
Lugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-growth-promoting rhizobacteria. Annual Review of Microbiology.
Salisbury, F. B., & Ross, C. W. (1992). Plant Physiology. Wadsworth.
Spaepen, S., Vanderleyden, J., & Remans, R. (2007). Indole‑3‑acetic acid in microbial and plant cross‑talk. Trends in Plant Science.
Taiz, L., & Zeiger, E. (2015). Plant Physiology and Development. Sinauer.
Wertheim, S. J. (1984). Training and pruning apple trees for productivity and quality. Acta Horticulturae.