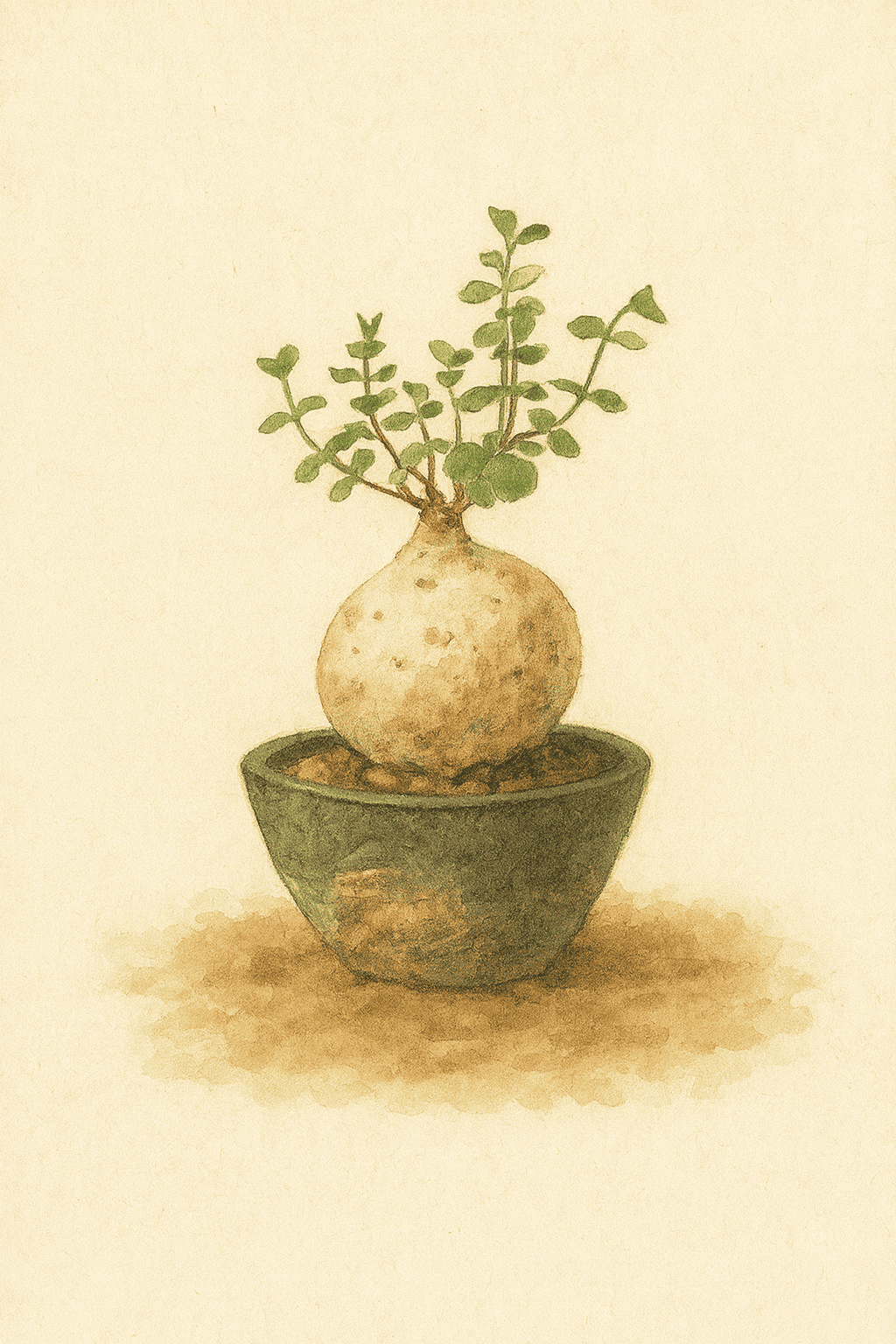はじめに:なぜ「CEC」を知ると塊根・多肉が美しく大きく育つのか 🌱
塊根植物や多肉植物を鉢で育てるとき、用土の「保肥力」をどう設計するかが、姿の美しさとサイズの伸びに直結します。ここで鍵になるのがCEC(陽イオン交換容量:用土が栄養のプラス電荷をつかまえておける力)です。CECは、施肥の効き方、塩分(EC)の溜まりやすさ、pHの安定性にまで影響します(Raviv & Lieth, 2008; Handreck & Black, 2010)。本稿では、CECの基礎から鉢植え特有のふるまい、資材の選び方、そして栽培シナリオ別の「適正レンジ」まで、論理の流れに沿って丁寧に解説します。ちょっと難しいかもしれませんが、CECについて知れば園芸スキルが一段階レベルアップするので、ぜひお付き合いください。
CECの基礎:単位・仕組み・「体積」で考える視点 🔎
CECは通常cmol(+)/kg(かつてはmeq/100g)で表します。CECとは、土の中にある粘土や有機物の表面が持つ小さな“マイナスの電気”が、肥料の中のカルシウムやマグネシウム、カリウム、アンモニウムといった“プラスの栄養”を引き寄せて、しばらくつかまえておける力のことです(Raviv & Lieth, 2008)。。
実務では、重量当たりの数値だけでなく体積当たりの有効CECが重要です。これは用土の密度で変わります。軽い用土は重さ当たりのCECが高くても、1Lあたりでは小さく見積もられます(Argo & Biernbaum, 1997)。したがって、鉢で考えるべき指標は鉢1つあたりの総CECです。例えば、CECが60 cmol(+)/kgで、充填密度が0.33 kg/Lの培地なら、体積基準のCECは約20cmol(+)/Lとなります(計算説明は後章)。
CECはpHや比表面積にも影響されます。特に有機物由来のCECはpHが上がると増え、下がると減る傾向があり(Brady & Weil, 2010)、培土では「測定値」と「実際の栽培pHで発現するCEC」がずれる点に注意します。
鉢植え特有のふるまい:潅水・溶脱・塩の蓄積の三角関係 💧
鉢では潅水のたびに溶けた肥料が底穴から出ていきます(溶脱)。CECがほぼない用土では施肥効果が長続きしません。一方、CECが高すぎる用土は肥料を強く保持し、EC(電気伝導度:溶けた塩分の濃さ)が時間とともに上がりやすくなります(Raviv & Lieth, 2008)。過度のECは根の水分バランスを崩し、葉先の焦げや萎れにつながります。温室研究では、培地(≒用土)のCECの違いよりも、施肥の頻度と濃度管理の影響が大きいことも示されています(Argo & Biernbaum, 1997)。つまり、CECは「便利なバッファー」ですが、過信せずECを定期的にモニターする姿勢が最重要です。
素材で変わるCEC:代表資材の目安と注意点 🧱
以下は、多肉・塊根でよく使う代表資材のCECの目安と、併せて押さえたいポイントです(Handreck & Black, 2010; Ming & Mumpton, 1989; Abad et al., 2002)。測定法やロットで幅が出ますが、設計時の参考になります。
| 資材 | CEC目安(cmol(+)/kg) | ひとこと |
|---|---|---|
| 日向土・軽石 | 3–8 | 通気抜群だが保肥は低い。微塵除去で性能安定。 |
| 赤玉土(硬質) | 20–40 | ほどよい保肥。経年で微塵化しやすい。 |
| 鹿沼土 | 5–15 | 軽く酸性寄り。用量は控えめに。 |
| パーライト | 1–3 | ほぼ保肥なし。通気・軽量化担当。 |
| ゼオライト(クリノプチロライト) | 100–180 | NH4+・K+保持に優れる。Na型は前処理推奨。 |
| バーミキュライト | 100–150 | 保水・保肥に優れるが泥化注意。 |
| ココピート | 30–95 | 中~高いCEC。Na・Kを洗浄/緩衝処理した製品を。 |
| ココチップ | 20–60 | 通気・耐久に優れ、CECは中程度。 |
| バーク | 50–100 | 微生物の住処にもなる。未熟物は避ける。 |
| バイオ炭 | 5–30(新)→50–150(経時) | 経時酸化でCECが増す。pH上昇に注意。 |
ゼオライトは、肥料に含まれるアンモニア態の窒素を特によくつかまえて離さない性質があります。そのため、一度つかまえた窒素を少しずつ植物に渡す役割を果たし、肥料の効き目を長くゆるやかに続けるのに役立ちます(Ming & Mumpton, 1989)。一方で、有機物はCECを足せる反面、酸素を消費する微生物活性が上がりすぎると過湿で根が傷みます。素材の組み合わせで、通気・保水・CECの三要素をバランスさせる発想が大切です(Handreck & Black, 2010)。
PHI BLENDの理論CEC:設計の考え方と数値の読み方 🧮
本メディアが推奨するPHI BLENDは、無機75%・有機25%というバランスで設計されています。具体的な各資材の配合比率は公開していませんが、主要な素材としては日向土・パーライト・ゼオライト・ココチップ・ココピートを用いています。ここでは、こうした資材を組み合わせたときのCEC(陽イオン交換容量)の理論的な考え方を紹介します。
まずCECは資材ごとに大きく異なり、日向土やパーライトのようにほとんどCECを持たない素材から、ゼオライトやココピートのように非常に高いCECを示す素材まで幅広く存在します(Handreck & Black, 2010; Ming & Mumpton, 1989)。それぞれのCEC値と乾燥密度を基に、ブレンド全体のCECは加重平均によって計算できます。
PHI BLENDのように無機と有機を組み合わせると、理論的にはおおむね中~やや高めのCEC(数十cmol(+)/kg程度)となります。体積当たりに換算すると、一般的な5号鉢(約1L)あたりで数十ミリ当量の陽イオンを一時的に保持できる計算です。カルシウムに換算すれば、根の成長を支えるのに十分な量をストックできる大きさになります(Argo & Biernbaum, 1997; Brady & Weil, 2010)。
実際の栽培では、pHや温度、乾湿の繰り返しによってCECの働き方は変わりますが、この「器の大きさ」を把握しておくことで、施肥設計を立体的に考えやすくなります。CECが高めであれば肥料成分をつかまえておける分、塩類の蓄積に注意が必要です。一方でCECが低ければ肥料切れが起こりやすく、頻度の高い追肥が前提になります。
なお、CECの大小はゼオライトやココ系素材のような高CEC資材の比率によって上がり、逆にパーライトや粗粒無機の比率が多いと下がります。ただし栽培の安定性を考えれば、CECを無理に変えるよりも施肥の濃度やフラッシング(たっぷりの清水潅水による塩抜き)の頻度で調整する方が安全です(Raviv & Lieth, 2008)。この考え方が、塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく」育てるための実践的なCEC活用の基盤になります。
どのくらいのCECを目指すか:シナリオ別の「適正レンジ」📏
CECは高ければ良いわけではありません。潅水頻度・施肥方法・栽培場所によって最適域が変わります(Argo & Biernbaum, 1997; Raviv & Lieth, 2008)。以下は、塊根・多肉を「綺麗に大きく」育てる観点からの暫定レンジです。
| シナリオ | 推奨CEC(cmol(+)/kg) | 施肥・ECの考え方 | Ca:Mg:Kの目安 |
|---|---|---|---|
| 室内・低頻度潅水(緩効性中心) | 15–30 | 緩効性少量+薄い液肥を月1。ECは常時0.5–1.0 dS/m未満。 | おおよそ 6:3:1(塩基飽和でCa優位)(Handreck & Black, 2010) |
| 室内・高頻度潅水(薄い液肥を毎回) | 5–15 | 毎回EC0.2–0.4で一定給肥。排水10–20%で塩をためない。 | 液肥ローテでCa, Mgを切らさない(Argo & Biernbaum, 1997) |
| 屋外・強日照・高蒸散 | 10–20 | 雨でリセットされやすい。成長期にやや濃い目の追肥も可。 | CaとMgをやや厚めに(Handreck & Black, 2010) |
| 発根・導入期(未活着) | できるだけ低く(<10) | 無肥~ごく薄い液肥。過浸透圧を避ける。 | 設定不要。まずは根を増やす。 |
いずれのシナリオでも、EC測定による見える化と、季節ごとのフラッシング(たっぷりの清水で塩抜き)が、CECを味方につける近道になります(Raviv & Lieth, 2008)。
品種差への配慮:アガベ/パキポディウム/ユーフォルビア 🌵
アガベは強光・強風でよく育ち、肥料が適度に効くとロゼットが大きく締まります。室内でもサイズアップを狙うなら、CECは中程度に設定し、Ca・Mgを欠かさない運用が安定します(Handreck & Black, 2010)。
パキポディウムは塊根に水分を貯め、過湿と高ECに弱い傾向があります。発根・導入期はCEC低めで無肥に近い管理が安全で、活着後にシーズン限定でCEC中程度の土へ移すと、肥大と形を両立しやすくなります(Raviv & Lieth, 2008)。
ユーフォルビアは種類差が大きく、繊細な種はEC上昇に敏感です。CECを欲張らず、薄い液肥を等間隔で与える方が、色艶を保ちやすい場面が多いです(Argo & Biernbaum, 1997)。
水とCEC:水道水の硬度がもたらす「見えない施肥」🚰
日本の水道水は概して軟水で、Ca・Mgの供給は少なめです(Hori et al., 2021)。潅水だけでCa・Mgを十分に賄うのは難しく、CECが中~高い培地ではCa・Mgの下支えを施肥で意識するとうまくいきます。一方、家庭用軟水器を通した水はNaが増えがちで、CECサイトをNaが占有すると作物に不利です。可能なら未処理の水・雨水・RO水を使い、CECサイトはCa・Mg・Kで満たす運用が無難です(Brady & Weil, 2010)。
実務手順:測る・整える・維持する 🧰
CECを「感じ」ながら運用する
CEC自体は家庭で直接測りにくいですが、EC(鉢底からの浸出液)と乾き時間、葉の色艶から間接的に把握できます。ECが上がりやすいのに乾きが遅い場合は、CEC高め+保水過多のサインです(Raviv & Lieth, 2008)。
塩基飽和の整え方
塩基飽和(ベースサチュレーション:CECの席をCa/Mg/K/Naが何%占めているか)は、栽培安定性に効きます。初期配合で石膏(CaSO4)や苦土石灰を少量混和し、CECサイトをCa・Mgで穏やかに満たしておくと、Ca欠・Mg欠に強くなります(Handreck & Black, 2010)。
フラッシングと植え替え
CECがあると塩は残りやすいため、季節の変わり目に徹底フラッシュ(鉢容量の2–3倍量の清水を通す)でリセットします。長期使用で微塵が増えたら、CEC云々の前に通気と構造を回復する植え替えを優先します(Argo & Biernbaum, 1997)。
PHI BLENDという選択:通気・保水・CECの折衷点へ 🌐
ここまでの議論を踏まえると、無機75%・有機25%で中程度~やや高めのCEC(理論値約60 cmol(+)/kg)を持ちつつ、通気性を損なわない配合は、室内・屋外のどちらにも運用で合わせやすい折衷点になります。PHI BLENDはゼオライトで栄養の持続性を補い、ココ原料で微量要素と水分の懐を持たせつつ、日向土・パーライトで通気を確保する設計です。塩の蓄積を避けるため、季節ごとのフラッシュとEC管理を前提に使うと、株姿を崩さずサイズアップを狙えます(Ming & Mumpton, 1989; Handreck & Black, 2010)。
配合や運用の詳細は、下記の製品ページをご覧ください。
おわりに:数字は道具、仕立ての主役は観察眼 👀
CECは数字で表せる便利な物性ですが、鉢の中では潅水と通気、温度、微生物が絡み合って動きます。紹介したレンジは出発点です。ECと乾き方、葉の反応を丁寧に観察し、施肥の濃さと頻度、フラッシングのタイミングで微調整してください。最小限のストレスで最大の健全さを引き出せたとき、塊根・多肉は自然に美しく、大きく育ちます。
塊根植物・多肉植物用土の全般に関する知識の整理は以下のページをご覧ください。
参考文献
Abad, M., Noguera, P., Puchades, R., Maquieira, Á., & Noguera, V. (2002). Physico-chemical and chemical properties of some coconut coir dusts for use as a peat substitute for containerised ornamental plants. Bioresource Technology, 82(3), 241–245.
Argo, W. R., & Biernbaum, J. A. (1997). The effect of root media on root-zone pH, calcium, and magnesium management in containers with impatiens. Journal of the American Society for Horticultural Science, 122(2), 275–284.
Brady, N. C., & Weil, R. R. (2010). Elements of the Nature and Properties of Soils (3rd ed.). Pearson Education.
Bunt, A. C. (1988). Media and Mixes for Container-Grown Plants (2nd ed.). Unwin Hyman.
Handreck, K., & Black, N. (2010). Growing Media for Ornamental Plants and Turf (4th ed.). UNSW Press.
Hillel, D. (1998). Environmental Soil Physics. Academic Press.
Hori, M., Azukawa, K., Sugimori, K., & Watanabe, Y. (2021). 日本の水道水硬度分布に関する報告(東京大学関連報告)。
Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). Biochar for Environmental Management (2nd ed.). Routledge.
Ming, D. W., & Mumpton, F. A. (1989). Zeolites in soils. In Minerals in Soil Environments (2nd ed.). Soil Science Society of America.
Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.