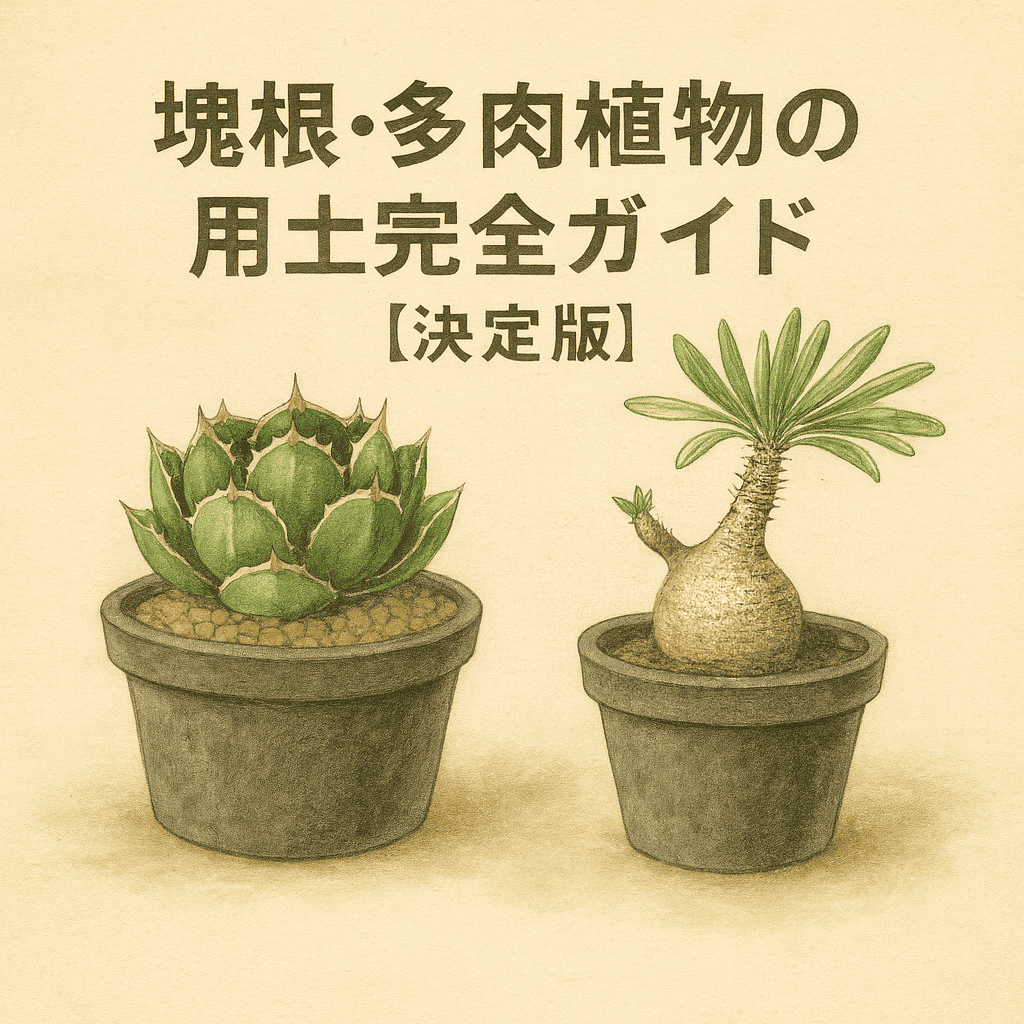
🌱 導入:なぜ用土が最重要か(本ガイドの読み方)
塊根植物や多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ためには、光や温度、風の管理と同じくらい、いえそれ以上に用土の設計が重要になります。用土は根の「住まい」であり、根は呼吸をして酸素を使い、水を吸い、養分を受け取ります。したがって用土は、通気性(空気が入るすき間)・排水性(重力で水が抜ける速さ)・保水性(必要な水分を保つ力)を適切に両立させる必要があります(Tjosvold, 2019;Handreck & Black, 2010)。本ガイドでは、査読論文や大学・農業試験場などの一次情報に基づいて、室内やベランダでの鉢栽培を前提に、用土設計の基準値・素材選び・季節ごとの運用までを、わかりやすく解説します。
🌿 用土の役割:根の呼吸・吸水・養分保持のしくみ
根は呼吸を行い、糖をエネルギーに変換します。このとき用土中の空気孔隙率(AFP)=「容器内の空気で満たされるすき間の比率」が一定以上必要になります。容器栽培ではAFP10〜25%(望ましくは20%前後)、全孔隙率(AFP+水で埋まったすき間)50%以上を確保すると、潅水後に重力水が抜けた段階で十分な酸素が確保されやすくなります(Tjosvold, 2019)。一方で、植物は水も必要としますが、量が多ければ多いほど良いわけではありません。用土中の水は重力水(潅水直後に抜ける水)と毛管水(細孔に引きとめられて根が吸える水)に分かれ、後者が主な水源になります(Hillel, 1998)。
養分保持の観点ではCEC(陽イオン交換容量)が関わります。CECは用土がアンモニウム(NH4+)やカリウム(K+)などの養分をつかまえる力です。適度なCECは「与えた肥料がすぐ流れ出ない」状態をつくり、肥料の効果を安定させます(Raviv & Lieth, 2008)。ただしCECが高すぎ、通気が不足すると塩類が滞留してEC(電気伝導率)が上がり、根に浸透圧ストレスがかかります。多肉・塊根ではEC0.5〜1.0 dS/m未満を日常の目安にして、定期的なリーチング(洗い流し)で蓄積した塩類を外へ出す設計が安全です(Colorado State University Extension, 2025)。
⚙️ 粒径と物理性(通気・保水・乾きの速度/鉢形状とパーチドウォーター)
💨 粒径分布が決める「空気」と「水」の座り方
粒径が大きいほどすき間が増えて通気性が上がり、乾きが早くなります。逆に細粒が増えると保水性が上がりますが、潅水直後の酸欠リスクも上がります。多肉・塊根には主粒径3〜6mmを基調にし、微塵(1mm未満)をふるい落としてからブレンドすると、AFPと水持ちのバランスがとりやすくなります(Tjosvold, 2019;De Boodt & Verdonck, 1972)。小鉢や室内で乾きが遅い環境では3〜5mmを中心に、屋外の風が強く乾きやすい環境では5〜8mmを一部混ぜて調整します。
関連記事:用土配合における粒径バランスの設計理論
💧 停滞水(パーチドウォーター)と鉢形状の関係
停滞水(パーチドウォーター)とは、用土の毛細管力によって鉢底付近に一定の高さで残る水の帯です。停滞水の「高さ」は用土の微細孔の大きさでほぼ決まり、鉢が浅いほど鉢容積に占める停滞水の割合が大きくなって根域の酸素が不足しやすくなります(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。浅鉢を使うときは粗い粒径を増やす、側面にスリットがある鉢を選ぶ、鉢底により粗い層を設けるなどして、実質的に停滞水帯を薄くします。逆に深鉢では上層の乾きが早くなるため、上層のみ細粒を1〜2割混ぜる層状ブレンドで水分分布を均しやすくします(Bunt, 1988)。
📏 乾きの速度を「数字」で捉える簡易法
日常管理では、鉢の重量を基準として覚えておく方法が実用的です。植え替え直後に「たっぷり潅水→一晩排水」のあと重さを測り、ほぼ乾燥時にも測ります。以降は手で持った重さの差で「水の入り具合」を推定できます。さらに表層の色(赤玉は湿ると色が濃くなります)を見たり、指で深さ2〜3cm堀ったところ湿り具合を感じたり、安価な土壌水分計を補助的に用いると、潅水判断が安定します(Handreck & Black, 2010)。
関連記事:水やりの頻度と量を決める4つの指標
🧪 化学性(pH・EC・CEC・塩類集積とリーチング設計)
🎯 pHの最適帯と調整方針
多肉・塊根の多くはpH5.5〜6.5の弱酸性〜中性で安定して養分を吸収します。ピートモス主体の土は酸性側に振れやすく、石灰資材で調整されていない場合はpHが3.5〜4.5まで下がることがあります(Raviv & Lieth, 2008)。配合で酸性材料(鹿沼土・ピート)を使う場合は、日向土やゼオライトなど中性〜弱アルカリの材料で中和します。水道水の硬度や潅水頻度でもpHは変化しますので、年1回程度の簡易pHチェックをおすすめします。
関連記事:土のpHが植物に与える影響とは|塊根植物・多肉植物の栽培における科学的検証
🚿 ECと塩類集積の管理
鉢栽培では蒸発と施肥の繰り返しで塩類集積が起きやすくなります。実務上はEC0.5〜1.0 dS/m未満を平常の目安にして、2.0を超える状態が続くと根傷みのリスクが高まります(Colorado State University Extension, 2025)。数ヶ月に1度、鉢底から十分な量の排水が出るまで潅水してリーチングを行い、表土に白い析出が見えたときは早めにリセットします(UC IPM, 2012)。
🧲 CECの意味と材料選択
無機質主体の配合は概してCECが低いです。その弱点を補う材料として、ゼオライトや少量の有機質(ココ由来・バークなど)を加えると、与えた肥料分を適度に保持して効きを安定させやすくなります(Ming & Mumpton, 1989;Raviv & Lieth, 2008)。ただしCECの過度な引き上げは塩分の滞留を招きますので、AFPとのバランスを優先します。
関連記事:CEC(陽イオン交換容量)とは:塊根・多肉の適正値
🧱 材料別の科学的比較(日向土・パーライト・ゼオライト・ココピート・ココチップ・赤玉等)
以下の表では、多肉・塊根の鉢栽培で頻用する材料について、物理・化学・衛生・長期安定の観点を◎/○/△/×で整理します。実際の評価は粒度や製法で変わりますので、注記と本文の根拠も合わせてご確認ください(Tjosvold, 2019;Raviv & Lieth, 2008)。
| 資材 | 物理性 (通気/保水) | 化学性 (pH/CEC等) | 衛生 | 長期安定 | 注記(根拠) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日向土(硬質軽石) | ◎/○ | ○(中性・低CEC) | ◎ | ◎ | 多孔質でAFPを確保しやすい一方、保肥は低いです(Tjosvold, 2019)。 |
| 赤玉土 | ○/○ → 経時で△ | ○(弱酸〜中性・中CEC) | ◎ | × | 経年で微塵化して通気が低下しやすいです(Handreck & Black, 2010)。 |
| 鹿沼土 | ◎/○ | △(酸性・低〜中CEC) | ◎ | △ | 酸性寄りで柔らかく砕けやすい性質があります(Xu et al., 2019)。 |
| 溶岩砂/スコリア | ◎/△ | ○(中性・低CEC) | ◎ | ◎ | 重いですが高通気で、保水は低い傾向です(Raviv & Lieth, 2008)。 |
| 川砂(粗粒) | ○/△ | △(中性・極低CEC) | ◎ | ◎ | 粗粒に限れば排水改善に寄与します。細粒は目詰まりを招きます(Handreck & Black, 2010)。 |
| パーライト | ◎/△ | △(中性・極低CEC) | ○ | ○ | 軽量でAFPを高めますが、潅水時に浮きやすいです(Raviv & Lieth, 2008)。 |
| ゼオライト | ○/○ | ◎(高CEC・NH4保持) | ◎ | ◎ | 肥効安定に寄与しますが、Na置換には留意します(Ming & Mumpton, 1989)。 |
| バーミキュライト | ○/○ | ○(中性・中〜高CEC) | ○ | ○ | 保水・保肥に寄与しますが、多肉では比率を低めにします(Raviv & Lieth, 2008)。 |
| ピートモス | △/◎ | ○(酸性・高CEC) | △ | △ | 過湿・撥水・キノコバエに注意します(UC IPM, 2012;Raviv & Lieth, 2008)。 |
| ココピート | △/◎ | ○(弱酸〜中性・中〜高CEC) | △ | ○ | 未処理品はNa/Kが多いので洗浄・Ca/Mgバッファが必要です(Abad et al., 2002)。 |
| ココチップ | ○/○ | ○(弱酸〜中性・中CEC) | ○ | ○ | 繊維より分解が遅く、通気維持に向きます(Abad et al., 2002)。 |
| バークチップ | ○/○ | ○(弱酸・中CEC) | △ | △ | 未熟品は菌源になりやすいので加熱処理品を選びます(Raviv & Lieth, 2008)。 |
| 竹炭/木質バイオ炭 | ◎/○ | ○(中性〜弱アルカリ・中CEC) | ◎ | ◎ | 通気改善・臭気低減・長期安定に寄与します(Lehmann & Joseph, 2015)。 |
📝 注:評価は標準的品質と中粒(3〜6mm)を想定します。極細粒を多く含めると酸欠リスクが上がりますので避けます(De Boodt & Verdonck, 1972)。
関連記事:
🏠🌬️🌞 室内・屋外・季節で変わる要件(光/風/温湿度との相互作用)
室内は光と風が不足しやすく、蒸散が弱いため乾きが遅くなります。したがって室内用は通気優先の中粒主体にし、有機質は20〜25%程度に抑えて過湿を避けます。一方、屋外の高温期や強風環境では乾きが速くなりますので、有機質や細粒をやや増やして保水を補うと安定します。湿度が常に高い温室では粗粒中心の配合と深鉢でAFPを確保します(Tjosvold, 2019)。冬は生長が緩慢になり肥料需要が落ちますので、施肥を控え、土のEC上昇を避けます。夏は蒸散が活発になり水切れが起きやすくなりますが、塩分も濃縮しやすくなりますので、月1回程度のリーチングで塩類集積を防ぎます(Colorado State University Extension, 2025)。
⚠️ よくある失敗と回避(目詰まり・酸欠・崩壊・虫/カビ)
最も多い失敗は目詰まりと、その結果としての酸欠です。赤玉土の微塵化や有機質の分解で細孔が埋まると、潅水後に重力水が抜けず、根腐れが誘発されやすくなります(Handreck & Black, 2010)。対策としては、微塵をふるい落としてから充填すること、植え替え時に表土の細粒層を除去すること、そして粒度を一定に揃えすぎないことが効果的です(De Boodt & Verdonck, 1972)。
虫害ではキノコバエが室内で問題になりやすいです。未熟な有機物と常時湿った表土が誘因になりますので、用土は有機質を控えめにして乾湿サイクルを確保し、黄色粘着板や表土砂敷き、必要に応じてBT剤で初期対応します(UC IPM, 2012)。カビの発生は見た目だけでなく根の呼吸を妨げますので、通風を確保し、表土に藻が出たら剥がして交換します。
関連記事:用土における虫の発生原理とその対策
資材の崩壊では赤玉土の長期使用が代表例です。硬質赤玉であっても1〜2年で粒が崩れて泥化しやすく、再利用は推奨しにくくなります(Handreck & Black, 2010)。無機主体配合は再利用に向きますが、再利用時は天日乾燥→ふるい分け→熱湯または太陽熱消毒を順に行い、古い有機分は半量入れ替えます。
関連記事:培養土に含まれる微塵とその弊害
🧭🧰 初心者〜中級者の運用プロトコル(配合→植え替え→初期管理→水やり再開)
📦 配合の基本
初めての方には、主粒径3〜6mm・AFP20%前後・有機質20〜25%・EC低めを満たす「中庸配合」をおすすめします。たとえば、日向土中粒、パーライト、ゼオライトなどの無機資材を75%、ココチップ、ココピートで25%という構成で、容器容量時の水分保持40〜50%、AFP15〜25%を狙います(Tjosvold, 2019;Raviv & Lieth, 2008)。
関連記事:無機と有機の役割と相互作用
🪴 植え替え手順
根鉢をほぐして古い土を落とし、腐った根や黒変した部分を切除します。用土は乾いた状態で鉢に充填し、棒で軽く突いて空隙を均一化します。植え付け後は直射を避けた風通しの良い場所に置き、3〜7日間は潅水を控えます(Ikeuchi et al., 2017)。これは傷口のカルス形成(傷をふさぐ組織づくり)を促し、病原侵入と酸欠を避けるためです。高温期に葉が萎れるときは葉水で凌ぎます。
関連記事:植え替え後の水やりはなぜ控えるのか?
🚰 初回潅水と以降の管理
断水期間後は、鉢全体をしっかり湿らせます。乾きが速い配合では二度潅水(最初に表面を軽く湿らせて毛管を起こし、5分後に本潅水)で全層に水を行き渡らせます。以降は鉢の重さ・表土の色・指の感触で乾きを確認し、完全に乾く手前で与えます。施肥は生育期に薄め(液肥ECで0.5 dS/m程度)から始め、数ヶ月に一度はリーチングで塩を抜きます(Colorado State University Extension, 2025)。
🧩 PHI BLENDの位置づけ(無機75%・有機25%の狙い、利点/限界、使い方のコツ)
PHI BLEND(無機75%・有機25%)は、通気性を確保する日向土とパーライトに、保水と保肥を担うココピート・ココチップ、さらにCECを付与するゼオライトを組み合わせた、バランス型の配合です。目的は「酸欠を避けながらも一日程度の水もちを確保し、塩類をため込みにくく、それでいて肥料切れもしにくい」環境をつくることです(Tjosvold, 2019;Ming & Mumpton, 1989)。
🔧 初心者でも安心な使い方フロー
- 鉢の準備 🪴
鉢底ネットを敷き、そのままのPHI BLENDを袋から出して充填します。ふるい分けは不要です。軽く棒で突いて、鉢内に大きな空隙が残らないようにならします。 - 植え付け直後の管理 🌥️
根鉢を整理して植えた後は、直射日光を避けた風通しのよい場所に置きます。3〜7日間は潅水を控え、根の傷口を乾かすことでカルス形成(傷を塞ぐ組織づくり)が進み、病害リスクを抑えられます(Ikeuchi et al., 2017)。 - 初回の水やり 💧
断水期間が終わったら、鉢全体をしっかり潤すように一度にたっぷり与えます。鉢底から水が抜けることを必ず確認してください。乾きやすい季節には「二度潅水」(一度目は表面を軽く湿らせ、5分後に本潅水)を行うと、全層に水が行き渡ります。 - 普段の水やり ⏳
鉢の重さを基準にして乾き具合を判断します。目安は「完全に乾き切る直前」で与えることです。表土の色や指先2〜3cmの触感でも確認できます。与えるときは少量ではなく、鉢底から水が流れるまでしっかり潅水するのが基本です。 - 長期利用の工夫 🔄
数ヶ月に一度はリーチング(鉢底から大量に流れるほどの水を通す)を行い、蓄積した塩分をリセットします。2年に一度を目安に、古い土を天日で乾燥・ふるい分けして微塵を取り除き、新しいPHI BLENDを少し足すと安定性が保てます。
⚠️ 注意点
・PHI BLENDは調整不要でそのまま使えるように設計されています。資材の追加やふるい分けは不要です。
・パーライトは潅水時に浮きやすいため、初回は用土を軽く湿らせてから植え込むと安定します。
・ココピート由来の微細粒子も養分保持と保水に役立ちますので、取り除かずにそのままお使いください。
📚 まとめ
塊根植物や多肉植物の用土設計は、粒径と空隙の調整による通気と保水の両立、pH・EC・CECといった化学的な安定性、そして病害虫を呼び込まない衛生的な管理の三本柱で成り立ちます。数値目安としてはAFP10〜25%、全孔隙率50%以上、pH5.5〜6.5、EC0.5〜1.0 dS/m未満を参考にしながら、環境や鉢形状に合わせて粒度や資材構成を工夫すると、根が健やかに呼吸し、塊根や葉が美しく充実していきます(Tjosvold, 2019;Hillel, 1998)。
参考文献
Abad, M., Fornés, F., Carrión, C., & Noguera, V. (2002). Physical properties of various coconut coir dusts compared to peat. Acta Horticulturae, 573, 215–221.
Bunt, A. C. (1988). Media and Mixes for Container-Grown Plants (2nd ed.). Unwin Hyman.
Colorado State University Extension. (2025). Leaching salts from potting mixes(資料番号 #1339)。
De Boodt, M., & Verdonck, O. (1972). The physical properties of the substrates in horticulture. Acta Horticulturae, 26, 37–44.
Handreck, K., & Black, N. (2010). Growing Media for Ornamental Plants and Turf (4th ed.). UNSW Press.
Hillel, D. (1998). Environmental Soil Physics. Academic Press.
Ikeuchi, M., Iwase, A., Rymen, B., et al. (2017). Wounding triggers callus formation via dynamic hormonal and transcriptional changes. Plant Physiology, 175(3), 1158–1174.
Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). Biochar for Environmental Management (2nd ed.). Routledge.
Ming, D. W., & Mumpton, F. A. (1989). Zeolites in soils. In Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 19, 1–60.
Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.
Tjosvold, S. A. (2019). Soil Mixes Part 3: How much air and water? University of California(Nursery and Flower Grower Blog)。
UC IPM. (2012). Fungus gnats – Pest Notes, Publication 7448. University of California Statewide Integrated Pest Management Program.
Xu, W., Sudo, S., & Takagi, T. (2019). 鹿沼土の話(1)—採掘から製品まで—. GSJ地質ニュース, 8(11), 301–307.