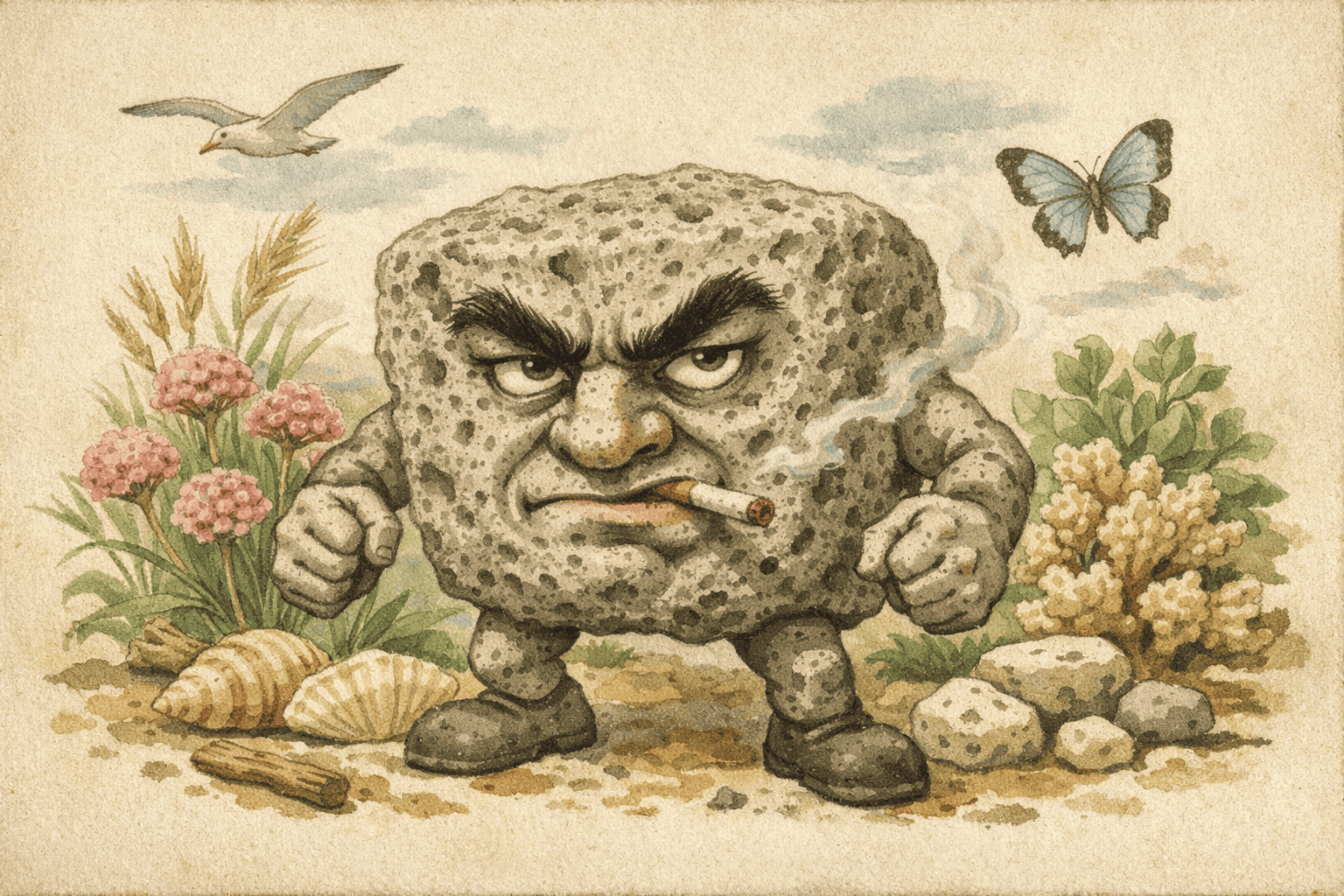✅ 結論(要約):軽石(パミス)は、粒子内部の微細な空隙と粒子同士のすき間が同時に働くことで、鉢内の空気孔隙率(AFP:Air-Filled Porosity=潅水後に空気で満たされるすき間の割合)を確保しながら、根が使える水分も一定量残しやすい無機質資材です(Sahin & Anapali, 2006;Tjosvold, 2019)。
✅ 要点:根域が水で満たされるほど酸素の移動は極端に遅くなり、根の呼吸(エネルギー産生)が落ちて傷みやすくなります。軽石は排水・通気を「孔隙構造」で支え、酸欠を起点とするトラブルを減らします(Hillel, 1998;Bailey-Serres & Voesenek, 2008)。
✅ 目安:鉢栽培では、潅水後に重力水が抜けた時点でAFPを10〜25%程度に保つ設計が、根の呼吸と管理性のバランスを取りやすいと整理されています(Tjosvold, 2019)。
塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく育てる」とき、最初に効いてくるのは肥料よりも、根がいる場所の空気と水の座り方です。ここでは軽石(パミス)を、経験談ではなく土壌物理学・植物生理学の言葉で分解し、なぜ塊根・多肉用土で頻繁に登場するのかを説明します。
目次: 軽石(パミス)とは何か|孔隙構造と「水はけが良いのに乾きすぎない」理由|鉢の中の酸欠と根の呼吸|停滞水(パーチドウォーター)と粒径設計
日向土・鹿沼土・パーライトとの比較|代表属別:軽石をどう効かせるか|化学性:pH・CEC・EC|衛生と微生物
実務に落とすチェックポイント|まとめ
軽石(パミス)とは何か:植物に効くのは「軽さ」より「多孔質」
軽石(pumice)は、噴火時に発泡したマグマが急冷して固まった多孔質の火山岩です。園芸の文脈で重要なのは、化学的な肥効ではなく、無数の孔を持つことで生じる物理性(通気・排水・保水の配分)です(Sahin & Anapali, 2006)。
軽石は一般に見かけ密度(バルク密度)が低く、鉢土を軽くしながら空隙を作りやすい資材です。たとえば容器栽培用の軽石を用いた研究では、粒径4–8mmの軽石の見かけ密度が0.40 g/cm³と示され、同じ研究内の土壌(約1.00–1.05 g/cm³)より大幅に軽い値でした(Sahin & Anapali, 2006)。この「軽さ」は結果であり、原因は粒子内部に空気を抱え込む孔隙(こうげき)にあります。
一方で、軽石は栄養分を供給する素材ではありません。むしろ無機質資材は陽イオン交換容量(CEC:用土がアンモニウムやカリウムなどのプラス電荷の養分をつかまえる力)が低い傾向があり、施肥設計とセットで考える必要があります(Raviv & Lieth, 2008)。同じく研究例では軽石のCECが6.9 cmol(+) kg⁻¹と示され、一般的な土壌より低い値でした(Sahin & Anapali, 2006)。
🌋 ここでの要点:塊根・多肉用土で軽石が評価されるのは、「何かを与える材料」だからではなく、根域の空気と水の比率を安定して作る「骨格材」だからです(De Boodt & Verdonck, 1972;Bunt, 1988)。
孔隙構造と「水はけが良いのに乾きすぎない」理由
軽石の理解は、孔隙(ポア)を大きさで分けると一気に明瞭になります。孔隙は大きさごとに、水・空気の役割が変わるからです(Hillel, 1998)。
容器培地の研究では、孔隙径を次のように区分して機能を説明することがあります。マクロ孔隙は排水と通気、ミクロ孔隙は保水、という対応関係です。具体的には、マクロ孔隙(>100 μm)が排水・通気、メソ孔隙(100–30 μm)が水の通りやすさ(導水性)、ミクロ孔隙(30–3 μm)が保水に寄与し、さらに小さい孔隙(<3 μm)に保持される水は植物が利用しにくい、という整理が示されています(Sahin & Anapali, 2006)。
🫧 軽石が強い理由:軽石は粒子内部にミクロ孔隙を持ち、粒子同士の間にマクロ孔隙を作りやすい形状をしています。その結果として、潅水直後に余分な水は抜けやすいのに、用土が完全に乾き切るまでの間に「根が使える水」を一定量残しやすくなります(Sahin & Anapali, 2006)。
実際、土に軽石を混ぜると、排水・通気に重要なマクロ孔隙が増え、同時に見かけ密度が下がることが示されています。軽石を50%(体積比)混和した条件では、マクロ孔隙(>100 μm)が98.2%および70.3%増加し、見かけ密度は24.8%および21.0%低下したという結果が報告されています(Sahin & Anapali, 2006)。
この「孔隙分布を動かす力」こそが、軽石が塊根・多肉用土で果たす中心的役割です。言い換えると、軽石は水を減らすのではなく、水がいる場所と空気がいる場所を分けることで根域環境を整えます(De Boodt & Verdonck, 1972)。
鉢の中の酸欠と根の呼吸:軽石が効く“生理学的”な理由
根は、糖を分解してATP(生体エネルギー)をつくる呼吸を行い、そのために酸素が必要です。鉢の中で問題になるのは、酸素の供給が「空気があるかどうか」だけでなく、「酸素が根まで移動できるかどうか」に依存する点です(Hillel, 1998)。
土が過湿になると、孔隙が水で満たされます。すると酸素の移動は急激に遅くなります。酸素の拡散係数は、空気中と比べて水中では約10,000倍遅いと説明されています(Hillel, 1998)。この差は桁違いで、鉢内の“酸欠”が短時間で起きる理由になります。
酸素が不足すると、ミトコンドリア呼吸が制限され、ATP産生が落ちます。その結果、根は養分吸収やイオン輸送などの能動的な働きを維持しにくくなり、組織の傷みが進みます(Bailey-Serres & Voesenek, 2008)。塊根植物・多肉植物は乾燥地に適応している一方で、根域の長時間の低酸素には強いとは限りません。したがって、鉢栽培では「乾かし気味」という管理方針そのものが、根の呼吸を守る戦略になります。
🧪 ここで登場するのが空気孔隙率(AFP)です。AFPは、潅水後に重力水が抜けた段階で、用土体積のうちどれだけが空気で満たされているかを表す指標です(De Boodt & Verdonck, 1972;Tjosvold, 2019)。
AFPについては、さまざまな実験と整理から「少なくとも10%は確保し、一般に25%を大きく超えない範囲が扱いやすい」という推奨が示されています(Tjosvold, 2019)。この幅が意味するのは、空気を増やしすぎると今度は水分保持が落ちて潅水頻度が過剰になりやすく、逆に空気が少ないと酸欠が起点になって根が傷みやすい、というトレードオフです。
軽石は、このトレードオフに対して「孔隙を増やす」と同時に「粒子内部に水を保持する」ことで、AFPを確保しながら水分も残す方向へ用土を導きます(Sahin & Anapali, 2006)。つまり軽石は、根の呼吸を守るという生理学的要請に、土壌物理で応える素材です。
停滞水(パーチドウォーター)と粒径設計:軽石が鉢底の環境を変える
鉢栽培では、排水穴があるのに鉢底付近に水が残ることがあります。この現象を停滞水(パーチドウォーター)と呼び、毛管力(細い孔ほど水を強く保持する力)によって起きます(Hillel, 1998;Bunt, 1988)。
停滞水の“高さ”は、鉢の高さよりも、用土の細孔の多さに強く影響されます。細粒が多い培地ほど細孔が増え、停滞水は厚くなりやすくなります(Handreck & Black, 2010)。浅鉢では鉢容積に占める停滞水の割合が大きくなるため、根域の酸欠リスクが上がりやすくなります(Hillel, 1998)。
⚠️ ここが実務の分かれ目:軽石を「鉢底石として敷く」だけでなく、用土全体の粒度分布の中に組み込むと、鉢全体の孔隙分布が変わり、潅水後に空気が戻る速度が上がりやすくなります(De Boodt & Verdonck, 1972;Handreck & Black, 2010)。
粒径設計のコツは、主粒径を数mmオーダーに寄せつつ、微塵(1mm未満の微細粒子)を必要以上に増やさないことです。微塵は保水を増やす一方で、排水直後のAFPを奪いやすく、酸欠側へ振れます(Handreck & Black, 2010)。塊根・多肉ではこの振れ幅が株姿(締まり)や根の事故率に直結しやすいため、軽石は「粒を揃えて、微細粒子を管理する」という使い方が重要になります。
日向土・鹿沼土・パーライトとの比較:似て見えて、孔隙の“質”が違う
軽石(パミス)と同じく「通気を上げる」目的で使われる資材に、国内で流通量の多い日向土、鹿沼土、パーライトがあります。いずれも培地の孔隙を増やしうる一方で、孔隙の作り方(粒子内孔隙か、粒子間孔隙か)、粒の安定性、経時変化が異なるため、狙いどころが変わります(Raviv & Lieth, 2008;Handreck & Black, 2010)。
| 資材 | 科学的に効くポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽石(パミス) | 粒子内外に孔隙があり、マクロ孔隙(排水・通気)とミクロ孔隙(保水)を同時に作りやすい点が強みになります(Sahin & Anapali, 2006)。 | CECが低くなりやすく、施肥設計とセットで考える必要があります(Raviv & Lieth, 2008;Sahin & Anapali, 2006)。 |
| 日向土(軽石質火山礫) | 粗粒骨格として粒子間のマクロ孔隙を確保しやすく、潅水後の空気孔隙率(AFP)を作りやすい資材として扱えます(De Boodt & Verdonck, 1972;Handreck & Black, 2010)。 | 微塵が増えると細孔が増えて停滞水帯が厚くなりやすいため、使用前のふるい分けで粒度を整えると再現性が上がります(Handreck & Black, 2010)。 |
| 鹿沼土(風化軽石) | 風化によって生成した非晶質成分(アロフェン等)を含むことが整理されており、軽石系の中では保水・吸着の振る舞いが変わり得ます(Xu et al., 2019)。 | 粒が崩れて細粒化すると孔隙分布が変わり、目詰まり側に振れやすくなります(Handreck & Black, 2010)。 |
| パーライト | 軽量でAFPを上げやすく、混合比で通気側へ調整しやすい素材です(Raviv & Lieth, 2008)。 | 非常に軽いため層分離しやすく、粒が壊れると微細粒子が増えて物理性が変わりやすくなります(Raviv & Lieth, 2008)。 |
🔎 同じ「無機質の通気材」に見えても、経時変化と粒度分布によって、鉢の中の酸欠リスク(AFPの低下)や停滞水帯の出方が変わります。次章では、この違いを前提に、アガベ/パキポディウム/ユーフォルビアで「どちらに寄せるべきか」を物理目標から具体化していきます(De Boodt & Verdonck, 1972;Handreck & Black, 2010;Tjosvold, 2019)。
代表属別:軽石をどう効かせるか(「配合比」ではなく「物理目標」から逆算する)
🌿 先に前提を揃えます。塊根・多肉の用土は、銘柄や配合比を当てに行くより、潅水後の空気孔隙率(AFP)と保水量(コンテナキャパシティ)のバランスを目標に置き、粒径と材料で近づける方が再現性が高くなります(De Boodt & Verdonck, 1972;Tjosvold, 2019)。
一般論として、容器培地では全孔隙率は50%以上を確保し、その中で水で満たされる割合(保水量)は少なくとも40%程度あると「約1日分の水需要」を満たしやすい、と整理されています(Tjosvold, 2019)。一方で、酸欠回避の観点ではAFPを10〜25%程度に保つ考え方が提示されています(Tjosvold, 2019)。この“枠”の中で、属ごとにどちらへ寄せるかを決めます。
🪴 アガベ:根の更新を止めないために「空気を確保しつつ、1日水持ちも残す」
アガベは乾燥に強い一方で、生長期には根がよく動きます。根が動くということは、根が酸素を使って呼吸し、イオン輸送などの能動的な働きを回しているということです(Hillel, 1998;Bailey-Serres & Voesenek, 2008)。鉢内が過湿になり孔隙が水で埋まると、酸素の拡散は空気中に比べて桁違いに遅くなり、根が「働けない時間」が増えます(Hillel, 1998)。
そのためアガベでは、軽石(主粒径3〜6mm程度)でAFP側を先に確保しつつ、管理上の潅水間隔を短くしすぎないために、保水寄与の材料を少量足して「1日水持ち」を作る設計が合理的です(Tjosvold, 2019;De Boodt & Verdonck, 1972)。ココピートのようなヤシ由来資材は、ピートに比べて性状が製品で変わるものの、培地の物理性を保水側へ動かす材料として扱われ、適切な洗浄・前処理を前提に利用されます(Abad et al., 2002;Raviv & Lieth, 2008)。
✅ 実務では「軽石で酸欠を避ける」ことを軸にし、保水は微塵ではなく設計した材料で足す方が、停滞水帯を増やしにくく安定します(Handreck & Black, 2010)。
🧱 パキポディウム:腐敗リスクを下げるために「停滞水を薄くし、乾湿の切り替えを速くする」
パキポディウムは塊根部(肥大部)を持ち、過湿条件で組織が傷むと回復が難しいことがあります。ここで効いてくるのが、鉢底付近に残りやすい停滞水(パーチドウォーター)です。停滞水の高さは鉢の背ではなく、主に培地の細孔(細かい孔)がどれだけ多いかで決まり、浅鉢ほど鉢容積に占める停滞水の割合が増えます(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。
したがってパキポディウムでは、軽石を「混ぜる」だけでなく、主粒径を粗めに寄せ、微塵(1mm未満)を必要以上に増やさない粒度管理が重要です(Tjosvold, 2019;Handreck & Black, 2010)。鉢形状も同じ理屈で効き、浅鉢を選ぶ場合は粗粒を増やす、側面スリットのある鉢で側方排水を助けるなどの方針が、停滞水の影響を小さくします(Bunt, 1988;Handreck & Black, 2010)。
⚠️ 植え替え直後の管理も科学的に説明できます。根の整理や切り戻しは傷(wound)を作る行為であり、植物はホルモンと転写のダイナミックな変化を伴いながらカルス形成(傷口を塞ぐ組織づくり)に向かいます(Ikeuchi et al., 2017)。この過程で過湿が重なると、物理的な酸欠と衛生リスクが同時に乗りやすくなるため、植え替え後に一定期間潅水を控えて乾かすという運用は、理屈として筋が通ります(Ikeuchi et al., 2017;Hillel, 1998)。
🌵 ユーフォルビア:タイプ別に「保水を足す幅」を決める
ユーフォルビアは属内の形態幅が大きく、同じ「多肉」でも根域設計を一括りにすると失敗確率が上がります。ここでは、土壌物理の目標値(AFPと保水量)を、タイプ別にどちらへ寄せるかで整理します(De Boodt & Verdonck, 1972;Tjosvold, 2019)。
茎が太く塊状に近いタイプや、根が繊細で過湿に弱いタイプでは、パキポディウム寄りにAFPを優先し、軽石主体で停滞水を薄くして乾湿の切り替えを速くします(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。一方、やや水分要求が高いタイプでは、アガベ寄りに保水量を確保し、潅水間隔の短縮を避けます(Tjosvold, 2019)。重要なのは「有機質を増やして保水する」のではなく、停滞水を増やしにくい形で保水を設計することです(Handreck & Black, 2010)。
化学性:軽石主体の弱点(pH・CEC・EC)を“数値”で扱う
⚙️ 軽石は物理性の設計に強い一方で、無機質主体の培地は化学的な緩衝(養分保持やpHの安定)が弱くなりがちです。塊根・多肉を「綺麗に大きく」育てるほど施肥と潅水の回数が増え、化学性のズレが表面化します。ここではpH・CEC・ECを最小限の数値で押さえます(Raviv & Lieth, 2008)。
🧪 pH:弱酸性〜中性の“吸収しやすい帯”に置く
多肉・塊根の多くは、pH5.5〜6.5の弱酸性〜中性で養分吸収が安定しやすいと整理されています(Raviv & Lieth, 2008)。ピートモス主体の培地は酸性側に振れやすく、石灰資材で調整されていない場合、pHが3.5〜4.5まで下がることがある、とまとめられています(Raviv & Lieth, 2008)。
軽石・日向土のような無機質材料は、強い酸性には寄りにくい反面、配合や潅水水質によってpHは動きます。したがって、年1回程度の簡易チェックで「帯から外れていないか」を見る方針が現実的です(Raviv & Lieth, 2008)。
🧲 CEC:肥料を“保持して効かせる”ための受け皿を作る
CEC(陽イオン交換容量)は、培地がアンモニウムやカリウムなどの陽イオン性養分を吸着し、流亡を緩和する能力の指標です(Raviv & Lieth, 2008)。軽石そのもののCECは高くないため、軽石主体の配合は「効かせた肥料が抜けやすい」方向へ寄ります(Sahin et al., 2005)。
この弱点を補う材料として、園芸ではゼオライトがよく使われます。ゼオライトは鉱物学的に高いCECを持ち、特にアンモニウム態窒素の保持などに関わることが整理されています(Ming & Mumpton, 1989)。無機質主体の配合に少量加えると、施肥の効きを安定させやすくなります(Ming & Mumpton, 1989;Raviv & Lieth, 2008)。
🧂 ECと塩類集積:成長を押すほど「根が焼ける」条件を作りやすい
鉢栽培では、蒸発と施肥を繰り返すことで塩類集積が起きやすくなります。実務上の目安として、培地のECは0.5〜1.0 dS/m未満を平常域とし、2.0 dS/mを超える状態が続くと根傷みのリスクが高まる、といった整理が示されています(Colorado State University Extension, 2025)。
軽石主体の配合は排水が良い反面、「少量潅水で済ませる」運用をすると塩が抜けにくくなります。したがって、与えるときは鉢底から十分に排水が出る量で潅水し、数ヶ月に一度はリーチング(たっぷり水を通して塩を流す)でリセットする設計が合理的です(Colorado State University Extension, 2025)。
衛生と微生物:軽石主体が“トラブルを減らす”条件を作る
🦠 多肉・塊根の事故は「水やりが多い/少ない」だけで説明できず、根域が酸欠になり、その上で衛生問題が重なると起きやすくなります(Hillel, 1998;Bailey-Serres & Voesenek, 2008)。軽石主体の配合は、この“重なり”を起こしにくい側へ環境を寄せます。
🪰 過湿+分解性有機物は、害虫管理を難しくすることがある
キノコバエ(fungus gnats)の幼虫は、湿った培地で有機物や菌類と関連して問題化しやすい害虫として整理されています(UC IPM, 2012)。もちろん、すべての有機質が悪いわけではありませんが、分解が進みやすい有機物が多く、かつ乾きが遅い条件では、衛生管理の難易度が上がり得ます(UC IPM, 2012)。
軽石主体の配合は、過湿時間を短くして酸欠を避けるだけでなく、結果としてこの種の衛生リスクを増幅させにくい側へ働きます(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。
🌱 無機質でも“生きた根域”は作れる
無機質主体だからといって、根圏が「無菌」になるわけではありません。根は糖やアミノ酸などを分泌し、微生物相を形成します。重要なのは、微生物相の善悪以前に、根が健全に呼吸できる酸素環境を維持することです(Hillel, 1998;Bailey-Serres & Voesenek, 2008)。軽石の孔隙構造がまずそこを支え、その上で必要な微生物相が落ち着く、という順序で理解すると論理が途切れません。
実務に落とす:軽石(パミス)を“事故らせない”チェックポイント
📏 ここからは、数値と物理の考え方を、日常運用に接続します。ポイントは「やってはいけない方向」を減らすことです。軽石の強みは、粒度を守るほど発揮されます(Handreck & Black, 2010)。
⚙️ 粒径の基本:主粒径3〜6mmを軸に、環境で微調整する
塊根・多肉の用土では、主粒径を3〜6mmに置き、微塵(1mm未満)をふるい落としてからブレンドすると、AFPと水持ちのバランスが取りやすいと整理されています(Tjosvold, 2019;De Boodt & Verdonck, 1972)。室内や小鉢で乾きが遅い場合は3〜5mm中心に寄せ、屋外で風が強く乾きやすい場合は5〜8mmを一部混ぜて調整する、という方針は物理的に合理的です(Tjosvold, 2019)。
⚖️ 「乾き」を感覚に頼らず、鉢の重量で再現する
潅水判断は、鉢内の水分状態が見えない以上、どうしてもブレます。そこで実用的なのが、鉢の重量で乾き具合を推定する方法です。たっぷり潅水して一晩排水した重さと、ほぼ乾燥時の重さを把握しておくと、以降は手に持った差で水分状態を推定できます(Handreck & Black, 2010)。
- 🧪 満水にして十分に排水させた後の重さを「基準(湿)」として覚えます(Handreck & Black, 2010)。
- 🧪 乾き切る直前の重さを「基準(乾)」として覚えます(Handreck & Black, 2010)。
- 🧪 その間のどこで水を入れるかは、属・季節・室温で調整します(Tjosvold, 2019)。
⚠️ ここで重要なのは、「毎回少量潅水で済ませる」方向へ行かないことです。塩類集積を避けるには、鉢底から十分に排水が出る潅水を基本にし、必要に応じてリーチングでリセットします(Colorado State University Extension, 2025)。
❌ よくある誤解:軽石を“鉢底だけ”に使って安心する
軽石を鉢底石として敷くこと自体が悪いわけではありませんが、停滞水帯は「鉢底に石を敷けば消える」という単純な話ではありません。停滞水の高さは主に培地の細孔に依存し、浅鉢では割合が増えるため、用土全体の粒度設計が重要になります(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。
✅ 軽石の効果を最大化するには、鉢底の層よりも、むしろ用土全体の孔隙分布として軽石を効かせる方が、根域の酸欠リスクを下げやすくなります(De Boodt & Verdonck, 1972)。
まとめ:軽石は「根域の酸素」を設計し、塊根・多肉を綺麗に太らせる
✅ 軽石(パミス)が塊根植物・多肉植物で重宝される理由は、肥効ではなく、鉢内の孔隙構造を通じて排水・通気・保水の配分をコントロールし、根が呼吸できる時間を増やせる点にあります(De Boodt & Verdonck, 1972;Hillel, 1998;Tjosvold, 2019)。
✅ 特に、停滞水(パーチドウォーター)と酸欠は、鉢栽培で避けにくい構造的課題です。軽石主体の粒度設計は、停滞水帯を厚くしやすい微塵を抑えつつ、AFPを確保する方向へ働きます(Hillel, 1998;Handreck & Black, 2010)。
✅ 一方で、軽石主体の配合はCECが低くなりやすく、施肥と塩類管理(EC)が“表に出やすい”側面があります。ゼオライトなどでCECを補い(Ming & Mumpton, 1989)、定期的なリーチングで塩をリセットする設計が合理的です(Colorado State University Extension, 2025)。
🌿 用土設計の一例として:PHI BLEND
軽石系の骨格を活かしながら、保水・保肥の不足を同時に埋めたい場合は、無機質75%・有機質25%の設計を一つの目安にできます(Tjosvold, 2019;Ming & Mumpton, 1989;Abad et al., 2002)。
たとえばPHI BLENDは、無機質(日向土・パーライト・ゼオライト)で通気性と排水性を作り、有機質(ココチップ・ココピート)で保水と保肥を補う、という役割分担の考え方に沿った配合です(Raviv & Lieth, 2008;Ming & Mumpton, 1989)。
参考文献
Abad, M., Fornés, F., Carrión, C., & Noguera, V. (2002). Physical properties of various coconut coir dusts compared to peat. Acta Horticulturae, 573, 215–221.
Bailey-Serres, J., & Voesenek, L. A. C. J. (2008). Flooding stress: acclimations and genetic diversity. Annual Review of Plant Biology, 59, 313–339.
Bunt, A. C. (1988). Media and Mixes for Container-Grown Plants (2nd ed.). Unwin Hyman.
Colorado State University Extension. (2025). Leaching salts from potting mixes(資料番号 #1339)。
De Boodt, M., & Verdonck, O. (1972). The physical properties of the substrates in horticulture. Acta Horticulturae, 26, 37–44.
Handreck, K., & Black, N. (2010). Growing Media for Ornamental Plants and Turf (4th ed.). UNSW Press.
Hillel, D. (1998). Environmental Soil Physics. Academic Press.
Ikeuchi, M., Iwase, A., Rymen, B., et al. (2017). Wounding triggers callus formation via dynamic hormonal and transcriptional changes. Plant Physiology, 175(3), 1158–1174.
Ming, D. W., & Mumpton, F. A. (1989). Zeolites in soils. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 19, 1–60.
Raviv, M., & Lieth, J. H. (2008). Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier.
Sahin, U., Ors, S., Ercisli, S., Anapali, O., & Esitken, A. (2005). Effect of pumice amendment on physical soil properties and strawberry plant growth. Journal of Central European Agriculture, 6, 361–366.
Tjosvold, S. A. (2019). Soil Mixes Part 3: How much air and water? University of California, Nursery and Flower Grower Blog.
UC IPM. (2012). Fungus gnats – Pest Notes, Publication 7448. University of California Statewide Integrated Pest Management Program.
Xu, W., Sudo, S., & Takagi, T. (2019). 鹿沼土の話(1)—採掘から製品まで—. GSJ地質ニュース, 8(11), 301–307.
::contentReference[oaicite:0]{index=0}